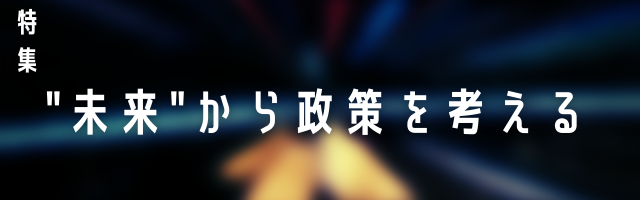京都大学こころの未来研究センター教授 広井良典
はじめに──AIは新型コロナ禍を“予言”したのか
真の意味で「未来」を予想ないし予測するというのは極めて難しい。
これについて、ある意味で私たちにとって一番分かりやすい例は、新型コロナウイルスによる感染症の拡大だろう。いうまでもなく、新型コロナウイルスの災禍で日本と世界の状況が一変した。しかし、今年の初めの時点で、誰がこうした事態の勃発と世界の変化を予想していただろうか。
つまりこれほど世界を大きく変えるような出来事を、誰も明確に予想できていなかったのであり、「未来」を予想ないし予測するのが難しいということは、この一つの例だけで十分に示されているともいえる。
しかし、実は今回の新型コロナウイルスによる災禍あるいはそこで浮かび上がった課題を、全く誰もが予想できていなかったわけではない。
手前みそに響いてしまうことを承知の上で記すことになるが、実は私たちの研究グループが3年半前に公表した、AI(人工知能)を活用した日本社会の未来に関するシミュレーションは、新型コロナ禍が明らかにした現代社会の課題を、少なくとも間接的には“予測”していたという面がある。
本稿では、そうした内容を紹介しつつ、「AIは未来の構想と政策提言に活用できるか」という話題を中心に考察を行ってみたい。
2 AIを活用した、持続可能な日本の未来に向けたシミュレーション
先ほどAIを活用した日本社会の未来に関するシミュレーションについて触れたが、それは具体的には、私が京都大学キャンパスに設置された日立京大ラボとの共同研究として行い、2017年9月に公表した研究である(ウェブサイト「AIの活用により、持続可能な日本の未来に向けた政策を提言」(1)及び拙著『人口減少社会のデザイン』(東洋経済新報社、2019年)参照)。
そこでは、現在そして未来の日本社会にとって重要と考えられる約150の社会的要因(人口、高齢化、GDP等)からなる因果連関モデルを作成し、AIを活用して2050年の日本に向けた2万通りの未来シミュレーションを実施した。シミュレーション結果として出てきたのは次のような内容だった。
① 2050年に向けた未来シナリオとして、東京一極集中に象徴されるような「都市集中型」と、「地方分散型」のグループがあり、人口、地域の持続可能性や格差、健康、幸福の観点からは地方分散型の方が望ましい。
② 2025~2027年頃に、都市集中型シナリオと地方分散型シナリオとの分岐が発生し、以降は両シナリオが再び交わることはない。後者への分岐を実現するには、環境課税、地域経済を促す再生可能エネルギーの活性化、まちづくりのための地域公共交通機関の充実、地域コミュニティを支える文化や倫理の伝承、住民・地域社会の資産形成を促す社会保障などの政策が有効である。
③ 2034~2037年頃に、地方分散型シナリオの中で持続可能性が高いものとそうでないものとの分岐が生じ、前者に導くためにはいくつかの政策対応が重要となる。
以上がAIシミュレーションの概要だが、今回の新型コロナウイルスをめぐる問題が、この「都市集中型か地方分散型か」というテーマと深く関わっていることはいうまでもない。今回の新型コロナ禍は「都市集中型」社会のもたらすぜい弱性や危険度の大きさを白日の下にさらしたというべきであり、あたかもAIが今回の新型コロナ禍をめぐる状況や課題を“予言”していたかのような関連性が見られたことになる。
私たちがAIを活用して行った以上のような研究は、他にあまり例がないものであったため、公表以降、政府関係機関や地方自治体、企業等から多くの問合せがあり、例えば自治体では2018年度に長野県庁(2)や岡山県真庭市(3)、2019年度には兵庫県(4)等と同様のAI活用を連携して進めた(以上の内容はいずれもウェブ上で閲覧可能)。その後も様々なタイプの同様の研究を進めてきており、また昨年から「ポスト・コロナの日本社会」に関するAIを活用した新たなシミュレーションを進めており、まもなく結果を公表予定である。