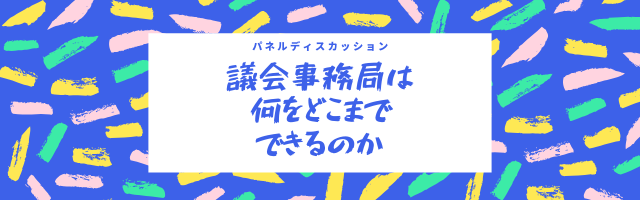議会図書室の活用
会場:西川さんにお聞きしたいのですが、議会事務局の職員も少なく大変ご苦労されているようですが、自治法上必置の議会図書室はレファレンス機能等々、活用すれば議会としての様々な政策を生み出していくツールとなると思います。その活用の仕方など、どのようにされているか教えてください。
西川:議会図書室は、書籍も閲覧できる状況にはなっています。ただ、議会図書室だけがあればということではなく、やはり議員の皆さんが調べたいときに必要な情報がそろっていることが大事ではないかと。ですので、議会図書室はもちろんですが、それに限らず、そういった環境を整えるということが重要なんだろうというように思っています。
清水:議会図書室の話については、大津市議会も本当に物置状態でしたので、数年前に改革に着手しました。その際に三重県議会の議会図書室も視察で見せていただいて、もう本当にすごいなと思いましたが、物理的な制約や予算の制約を考えると、そのまま真似するのは現実的ではありませんでした。大津市議会でも蔵書の充実とか、図書館司書を自前で置くとかしたいんですが、まずは近隣大学の図書館と連携して、学生さんと同じパスカードを議員全員にもらって自由に大学の図書館に入れるようにして、レファレンスも大学図書館の司書から受けるような政策を組み立ててフォローすることとしました。いずれは議会図書室自体も整備したいんです。自前の司書を置くっていうのは大事だなと思っています。ただ、レファレンスを司書から受ける習慣が議員にまだ根付いていないので、そこへいくまでのステップとして大学図書館との連携等をやっています。
谷畑:ちなみに湖南市では、議会に対してレファレンス機能を強化するべきとしまして、市立図書館の司書を二人議会事務局に配置したいと議長に申し上げました。しかしお断りをされまして、現在は市立図書館の司書二人を議会事務局の兼務発令をしている状態です。まだレファレンスをどう活用するかという、そこの慣れがないということはあると思います。
全国の自治体議会においても、やはり同じような状況ではないか、何かしたいと思ってもそれを実現する手立てというか、手段というか、積み重ねのルートが見えていないという議員がたくさんいるのではないかと思います。いかに議会事務局がサポートしながら、潜在的な政策の種を浮き上がらせて政策化できるかというのも非常に大事な論点なのではないかなというふうに思います。

議員提案の財源措置の課題
会場:政策提案のお話をお聞きして、財政の部分が出てこなかったので、そこが気になります。議会の政策提案といっても、条例の条文の確認であれば法制担当に確認ということでいいと思いますが、予算措置が必要なものは当然財政の部分の確認が必要だと思います。その点を議会事務局はどのようにしていくのかというのと、議員のほうが無責任に政策提案をしても財源措置が難しいというものがあればブレーキをかけたり、といったこともあるかと思いますが、いかがでしょうか。
林:西脇市議会では、以前政策提案の場で、「財源のことも考えなければいけない」という提案をしたんですが、多くの議員から、「それは執行部が考えることや」と一蹴されまして、それ以来進んでおりません。
清水:今まさに大津市の中でも議論になっているところです。公営ガス事業を売却してまとまったお金を、他の政策の基金に使うというような補正予算が提出されているんですけども、それに対してどう対応するかということです。修正案を出すにしても、具体的な考えがないと出せません。代案を示すっていうのは本当に大事なことです。反対意見を出すのは簡単ですけれども、代案を出そうと思ったら、本当に財源の部分を検討していかなければいけません。従来修正案を出すときにやったのは、財政調整基金のところで出し入れをするくらいでした。予算案全体の修正がいるときには組み替え動議を出すということですけれども、それが正解だとは思えません。また、全体的なものの修正をしたことはまだありませんが、今後の検討課題だとは思っています。
谷畑:ありがとうございました。まだまだご質問、ご意見もあろうかと思いますが、そろそろ予定していた時刻となってまいりました。今日はですね、議会の存在意義を問うという中において、議会事務局がどういったことができるのだろうかということについて皆さんで議論を深めさせていただきました。議会の事務局の在り方につきましても、規模、自治体の規模、また議員の側から職員の側から、色々な見方があるということがおわかりになったと思います。
これからも様々な課題があろうかと思いますし、今日出されました課題もあります。また議会事務局研究会のほうでも議論を深めてまいりたいと思っております。色々なお話をいただきました5名のパネリストの皆様に、皆様から拍手をいただきたいと思います。これをもちましてパネルディスカッションを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。