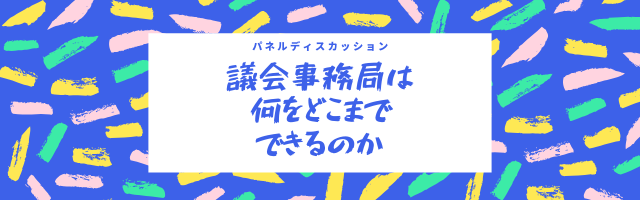委員会の重要性
会場:色々と皆さんのご意見をお伺いして感じたのが、委員会の重要性です。委員会の政策提案も有効ですし、単独の議員が提案すると「あいつが言っているから」とはなから否定されてしまうパターンが多い中で、委員会にはメンバーが各会派から来ていますので話し合いの場所として、様々なアイデアが具体的になっていく可能性が大きいと思っています。
以前神原勝先生が仰っていたのが、第二部類の委員会として各部署の委員会を作るのもあるんだけど、地域別に議員さんが集まって委員会を作ってもいいんじゃないか、そして地域のことは委員会の中で話し合ってみてもいいんじゃないかということです。
パネラーの皆さんにお伺いしたいのが、委員会の可能性と今後の展開です。何か具体的な展望があれば、議会事務局の職員も手伝いやすくなる、応援しやすくなるんじゃないかと思ってお伺いさせていただきます。
林:委員会の重要性は、私もよく理解しているところです。委員会改革でまず何をやるべきは、所管事務調査の充実です。委員会の専門性を高めるにはそれしかありません。所管事務調査が充実していない委員会に議案を付託したところで、それは単に少人数で審議しただけなんですよ。そこには専門性も何もないんですね。所管事務調査を普段からずっとやっていることによって、委員会としての専門性が磨かれます。そういう委員会が審議した議案であれば、本会議にかけたときに委員会の結果を重視して採決に臨むという形をとれるのではと思います。
宮下:私も委員会はすごく重要だと思っています。ただ、実は月形町には常任委員会一つしかないんです。「まちづくり常任委員会」といって委員は8人、議長はオブザーバーの形で抜けるんですけれども、本会議と常任委員会と全員協議会も全員参加ですからみんな同じ人数なんです。だからこそ、それぞれの色分けを逆にはっきりさせていて、本会議は議員間討議はできないので討論という形になります。常任委員会は所管事務調査で説明を受けたあと、説明員が退席し、委員で一応自由討論という形をとっていて、それぞれの想いなり問題点、課題の抽出、指摘などをします。全員協議会では、もっと私的な、内部の話ができます。このように、それぞれ位置づけを明確に分けるようにしています。
委員会は本当に自由な議論をしています。月形町議会では、委員会は議事録を作成せず要点筆記だけです。そういう扱いにしているのは事務の簡素化という側面が大きいですが、逆にそういう扱いだからこそ自由に話ができると考える方もいらっしゃるようです。本会議のようにきちっと議事録が残されてしまうのでは発言は難しいと思ってらっしゃる方々がいます。議員同士で議論するためにはお互いの配慮も必要であると思いますし、議論することが一番大事だと思っているので、こういう形で今後もいけたらなと思っています。
杉山:私も委員会審議の充実は、非常に大事だと思います。その中で一番大事なのは議員同士で議論するということだと思います。ただ、議論を深めるということについて、執行部に質問で追及することであると考える議員もいるかなと思います。議会内で、議員同士で本格的に議論することはあまりないんです。角が立つこともあって議員同士で議論をするのを避けているような感じもします。他方、議員同士ですごく激しい議論をすることがあるとすれば、ほぼ政争に近い場合です。大阪府の場合、大阪都構想、大都市制度をめぐる議論はありますが、ほかの案件、住民生活に密着した福祉の話とか医療の話とか教育の話で、議員同士で委員会を使って積極的に議論するっていう場面は大阪府議会の中ではあまり見られません。理事者を質す、知事を追及すると、これが活発な議会だと考える先生方が多いのかなという気がします。
清水:委員会主義をとっている議会は特に、委員会で活発に議員間討議ができる仕組みづくりなり文化を作ることが必要だと思います。大津市議会では所管事務調査に対する議員間討議の時間は、執行部職員を部屋から出してから行うことにしています。先にお話があったように執行部を入れて討議をすると、議員はみんな執行部に向かって発言するので、執行部に退席してもらったあとに、議員間討議をするという工夫をしているわけです。
それから、本会議=討論ということにも疑問を持っていまして、自治法上「本会議」と規定しているのは、法は「会議」を期待していると思うんですよ。ところが現状の本会議の場は一方通行的なもの、質問や討論、採決とか、がほとんどです。あれのどこが会議なのか。本当は、本会議と呼ばれるところで議員間討議がなされるのを地方自治法は予定しているのに、「委員会主義」という名のもとに委員会にそれを振ってしまって、本会議は形式的になってしまっているのではないかと思います。だからその辺も法律の立法趣旨に反して全国的にあるべき形と違う方向に特殊進化してしまっていると思います。将来的には本会議の中で議員間討議ができるようにすべきだと思うんですが、当面はまずは委員会の場で議論する、そういうところから順番に改善していくべきと私は思っています。
西川:寝屋川市でもほぼ状況は同じです。委員会主義を採っているので、議員の皆さんは活発に質疑応答して行政側を問い詰めるということにかなり時間を割いて取り組んでおられます。他方で、なかなか議員間討議の活発化や委員会として活動を重視しようという動きにはなかなかいっていません。委員会としてできることは、政策提案など含めてもっとあると思いますが、なかなかできておりませんので、まずはそれが議員の間に根付くような取り組みが必要なのかなと思っております。
広域自治体議会と基礎自治体議会の連携
会場:先ほどの林さんのお話で、自治会単位で年に40回くらい議会報告会を開催しているとお聞きしました。それとは別に、たとえば兵庫県議会と西脇市議会の交流や、政令市である神戸市会との交流など、そういうことは何かやられていますでしょうか。現在三重県議会では各市町の議会との交流をやっておりまして、たとえば防災とかその時々でテーマを設け意見交換をし、市町議会の声を県議会の議論の中にどう反映させるかや県議会の考え方を市町の議論の中にどう活かしてもらうかといったことを試行的に行っています。まだうまくいっているとは言えませんが。ですので、そういう取組みがあれば、ぜひ教えていただきたい。
林:県議会とか政令市の神戸市会との交流はないです。全くありません。議長会としてはやってますけど、県議会の方も議長会の会長、副会長、理事なんかと意見交換会を、私は実は副会長なのでそういった場面での交流は行っていますが、市議会単位としてはないです。
清水:議会間の連携についてです。実は先日福井県議会に事務局職員研修の講師として呼ばれたのですが、その際に福井県内の他の市町の事務局にも声をかけて研修を実施されてたんですね。そういう例って私の知る限りではありません。議長会の単位で研修を行うのは普通にどこでもやっているんですけれども、広域自治体議会が基礎自治体議会に声をかけて連携する動きは初めて見ました。
その新しい動きを見て、気づきがありました。それは、執行部であれば広域自治体が基礎自治体の能力の足りないところを事務的に補うという仕組みが法定されているのに、議会になるとそれぞれスタンドアロンになっているということです。ただ、法が予定してなくても、任意で取り組んでいくことはできます。広域自治体議会のほうでそういう意識を持って、基礎自治体の議会に接していくような、そういう考え方、動きをとってもらえたらいいかなという風に思い立ったところです。