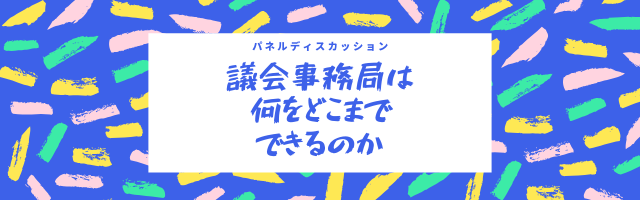大きな議会と小さな議会
谷畑:ありがとうございます。宮下議員の月形町は、とりわけ人口3,000人の町ということでありまして、そんな中で女性、若者、そしてよそ者として……色々とご苦労や悩みなどもあろうかと思います。
また、先ほどにもお話ありました、自治体は中央の下請けではないという思いも持っておられるように思いますけれども、外からの議会改革論に対する思いなどもお話をいただけたらなと。内からの改革論や議会事務局改革について何かご提案があればよろしくお願いします。
宮下:議長の下に議会事務局がありますから、委員会のサポートとか公的なことについて事務局はきちんとやってくれます。たとえば、委員会として政策提案をしたいという希望があれば、そのときには事務局は、少人数ではありますが、色々と工夫をして協力をしてくれます。他の議会に問い合わせをしたり、執行部の法務担当にサポートいただいたりしながら議案を作るということもしてくれます。
しかし、たとえば私個人が「何かやりたい」というときには、先ほどから話に出ております「公務員は全体の奉仕者」というお話を事務局は常にされます。「議員一人に対してはそんなことはできません」ということでサポートは受けられません。私の議会ではそういう調子ですから、大きい議会では会派に対してのサポートがあるというのを聞いたときに、率直に素晴らしいなと思いました。他方、大きい議会はやはり政治的な動きも多いということもお聞きしました。小さな議会の議員である私が、色々な改革をしたり、提案したりすることは純粋な議事に対する取り組みといった感じで、政治とはあまり接点がないことがほとんどです。だから「会派のサポート」と一口にいっても大きな議会と小さな議会でとらえ方が全然違うというふうにも今日お話を聞いていて感じました。
ところで、議会事務局長が変わると、事務局の姿勢も変わったりすることはあります。仕事のスタンスや会派への関与も、その時々の事務局長でそれぞれ考え方が異なるところもあって。たとえばある議会事務局長は基本的に「公務員としての全体の奉仕性」っていうのは守るけれども、私が一人で提案したことも「それは議案の修正で本会議にかかわることだから」という、より踏み込んだ解釈をしてくれてすごく積極的に関わってくれて、その議会事務局長がいたときは私も修正案2、3本出したり、物事が進むということがありました。でも、そういう方が定年退職するとか異動したりして、局長が別の方に代わったりすると「一切できません」というふうになって進まなくなってしまう。そういうときに、議会事務局の重要性をものすごく感じます。
議会を改革する、新しくするためには、やっぱり議会事務局側の考え方は大事です。私たち議員も法的な面とか色々に解釈しながら改革を進めていくわけなので、同じベクトルに向いている事務局と協働できれば、議会改革はものすごく進むという感じを受けています。それがうまくいっているのが多分栗山町議会だったり芽室町議会だったりするわけで、議会改革創成期にそういう議会がスタートを切って、周りが影響を受けて巻き込まれて、システムとして構築されていくっていう形にまで持って行けたと思うのです。けれども、私の議会ではまだ全体的に議会改革の機運が高まっているというわけではないので、議員個人の資質どまりになっているのかなと考えています。
情報公開をどう進めるか
宮下:「事務局による手厚い会派サポートもあって、議会改革の取組みなど色々なことが会派内で検討され、会派会議で決まって、どんどん進んでいる。けれども、会派内で固まった形で表に出てくることもあって、本会議とか委員会で議論はほとんどない」という話もありました。
私は、議会改革の本質は、情報公開と住民参加だと思っています。私が町民だったら、今議会で何が話し合われて、どういう経過でこうなったのかが知りたいです。ここが私の出発点になって、議員に立候補したときから情報公開と住民参加っていうことが私のメインテーマになっていて、ずっと活動を続けてきています。だから、たとえば本会議など住民に目に見えるところで議論がなされるスタイルに持っていくことが本質的な改革だと思っているんですね。でも、会派サポートを追求していくと、どんどん内側に後退していって、本会議ではなくて委員会、そして会派会議…みたいにどんどんどんどん後ろに行ってしまって、情報公開というところから遠ざかっていくように思います。それは本質的な議会改革ではなく、先ほども指摘しましたが、政治的なもの、政争の方に傾いていってしまっているという印象があります。
小さな議会は、町民との距離が近いこともあって、情報公開と住民参加をものすごく求められています。個人としても議会としても、常にそれらを突き付けられているので、そういう意味では小さな議会は変われるチャンスが沢山あります。暮らしの延長線上にある基礎自治体はそうあるべきでだと思いますし、そういう方向で進められたらなと思います。自治体のサイズの違いや、方法論の違いなど、皆さんのお話を色々と聞きながら、そんなことを考えました。
谷畑:ありがとうございました。会派で物事が決まって表に出てこないという点については、どうでしょうか。
杉山:課題だと思いますね。現状の法制度では、会派は私的団体なので、会派内でやりとりされていることは、基本的に表に出てきません。情報公開の請求の対象外でもあります。どういう過程で物事が決まったのかということが文書にも残りません。最終形だけが議案として出てきて、そのときには賛成反対含めて会派間の調整も水面下で行われた状態です。大阪府議会は全会一致の議案は調整に時間をかけますが、表に出てくるときは提案説明や討論、委員会付託も省略されます。議案の番号だけがわかる状態で、簡易採決で通ることになります。このように実態として規模が大きな議会である都道府県議会、大阪府議会の場合は会派間や会派内での調整がメインで色々物事が進むため、議案に至る過程が非常に見えにくくなっています。会派は政務活動費の受け皿ではあるのですが、どこかでその法的な位置づけ、公的な位置づけを明確に与えることが必要かもしれません。それによって、もっと会派内での検討過程や会派間の調整など、議案に係る様々な情報が、公に出てくるようになるのではないでしょうか。
谷畑:ありがとうございます。お話をお聞きしまして、やはり、大規模議会での議会改革というものは、月形町や西脇市議会など比較的規模の小さな議会と比べてみて、課題とするべき点や改革の着眼点が違ってくるところもあるのかなと、思いました。
この後、会場の皆さんとやりとりをさせていただきながら、さらに議論を深めていきたいと思います