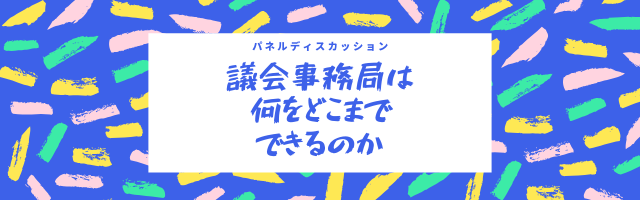会派の法的根拠
谷畑:清水さんにも同じことをお伺いしますが、それと併せて会派活動のサポートについては公務員の全体の奉仕性との絡みがどうなのかというようなことについても少し触れていただくとありがたいかなと思います。
清水:大津市議会においても会派制を取っていますし、議会局職員の中でも会派担当という職務を与えている職員はいます。ただ大阪府議会さんのように、会派の中にデスクを構えて常駐しているスタイルではないです。純粋な会派活動にかかわる職員の在り方というのはほとんどの場合違法だと私は考えています。というのは、会派の法的根拠というのが、政務活動費の支給先としてしか定義されていないからです。事務局の職員は公務に携わるというのが大前提で、公務として定義されるのはあくまで本会議にかかわる事務、委員会にかかわる事務、そのほか議長が議会の代表者として動く部分の活動の補佐、そのほか議員派遣をとった部分での議員のサポートというようなことしか公務として認定されないのです。会派活動自体が公務ではないので、いわゆる純粋な会派活動に携わるというのは、違法行為だと思います。
ただし、会派単位で議案の修正案を出すとかそういう部分の手助けであれば、それは政党色がつかない純然たる、議案に対する、本会議審議にかかわる事務の部分であるため、それは積極的にかかわってかまわないと、考えています。
谷畑:次に西川さんにお伺いいたしします。委員会活動に対してのサポート、会派活動のコミットに対する体制と状況はいかがでしょうか。また、議会事務局職員、先ほど2名削減されたというお話でしたけれども、質的向上が必要ではないかということ、議会の体制強化についても触れていただければ。
西川:まず委員会活動のサポートについては、議事の担当というのは当然つけてはいます。しかし、現状では「調査」の担当という役割までは担えていません。事務局のサポート体制が十分に整っているとまでは言えないと思っています。職員数が減ったことに気を遣っていただいていることもあってか、議員からの依頼も以前より減っています。
ただ、事務局に頼らずとも様々な個人的なネットワークを駆使したり、窓口で調査をされたりということができるベテラン議員もいますが、新人議員では最初からそういうわけにもいきません。そうなると、委員会が、議員個人の力量任せにどうしてもなってしまうのかなと危惧しています。やはり委員会の機能を発揮するという面では好ましくないという状況と認識しています。一方で、調査のサポートには、やり方は色々あろうかと思っています。事務局が全てやるということでなくインターネットや書籍、議会関係の書籍もかなり充実しておりますので、議員がそれらを十分活用すればかなり調べることができるかなとも思います。
ところで、全国的に他自治体について調べるような調査の場合、事務局が代わりに調査をすることになります。実は寝屋川市は2019年4月から中核市になったのですが、照会がかなり増えまして、びっくりしています。1日1市以上くらいのペースで照会が来ております。他の議会も含めて、事務局の人手に依存しての調査ばかりというのもどうかということもありますので、中小規模の議会なりに工夫してやっていきたいと考えています。
会派のサポートについていえば、寝屋川市は職員数が少ないこともあって、会派の担当というのは元々ありません。駒林(良則)先生のお話にもあったように、会派の制度化という議論が出てきています。職員が会派活動に携わることへの違法性も指摘される場合もあるということですので、法制化されるとその辺の問題がクリアになるかなと思います。それから、個別の会派ではなくて議会全体でしかサポートできないというふうになってしまいますと、どうしても大きな会派中心のサポートに偏ってしまうという傾向があるかと思います。会派別のサポートができると、少数会派の活動についてもサポートすることができるので、少数の民意も議会に反映する体制ができるのかなというとことで、こういった法制化はメリットがあるのかなと思っております。
事務局のサポート体制構築の課題
西川:議会全体として条例立案をするというときには、当然事務局としてサポートしているという状況です。ただ、現状の議会事務局に法制執務を経験した職員が配属されているというわけではないため、実際に政策立案のサポートが十分できるという体制にはなっておりません。実は3年前に一度だけ議員立法に私も関わらせていただいた経験があります。議員提案条例という体ではありましたが、実際の立案の作業というのは執行部の方に協力をお願いしまして、事務局としてはパブリックコメントの手続きや関係者の調整等のサポートにとどまりました。事務局は立案の中核の部分には関われないというような、議会単独での政策提案とはいいがたいものではありました。実は役所内にも法制執務を経験した職員というのが数少なく、執行部側でも人材が足りていない状況にあります。そういう中でそういった職員を議会だけに専属させるのは事実上大変厳しいのかな、と。
このように、私どものような中小規模の議会で議員立法をコンスタントに取り組んでいくのは現実的に難しいこともありますが、今年2月の議会事務局研究会の方で西脇市議会の林議長から議員立法についてお話があったことがありました。それは西脇市議会で取り組んでいる委員会の政策提案についてでした。中小規模の議会にとってはすごく有効だと思っています。大規模議会とは異なり、中小規模議会では身近なテーマを取り上げやすく、また、そういうテーマですと議会としてまとまりやすいということもあります。また、委員会からの政策提案ということになりますと、非常に説得力が出てくると思います。場合によっては、またそういった政策提案の具体的な中身を、条例の立案を提案するということにすれば、間接的な形になるかもしれませんが、議会が立案の方に関わっていけるということにもなろうかと思います。このように、中小規模の議会だからこそできること、大規模じゃないのでできないところもあるんですけれども、中小ならではの工夫もやっぱり自分達で考えて実行していかなければならないかなと感じるところです。
最後に、先ほどから議会事務局の体制が少ないからできないと、何回も言い訳をしてしまっているんですけれども、人数少ないと言ってしまったら本当にこれ以上前に進まないということもありますので、少なくともできることからこつこつとやっていく、もしもどうしても限界がきたら議長に訴えて自分たちの取り組みを認めてもらったうえで体制がさらに拡充が必要だったらお願いするということで、そういった環境整備をぽつぽつとやっていく必要があるのかなと考えております。
谷畑:ありがとうございました。ここで一旦、会場からご質問をお受けしたいと思います。
会場:議会事務局の職員が会派をサポートすることについて違法ではないかという清水さんのご発言についての質問です。大津市議会の議会基本条例には、会派についてちゃんと根拠づけがあります。会派とはどういったものか、役割についても書いてあるんですね。同じような規定が京都市会の基本条例にもありますけれども、このように条例に根拠があれば別にかまわないのではないかと私自身は考えたんですけれども、いかがでしょうか。
清水:法律に書いていない限りは、会派のサポートを公務として位置付けて、どっぷり入るのはアウトかなという解釈をしています。大津市議会では、議会としての政策立案を全体として取り組む仕組みを作っているので、会派提案の政策条例は大津市議会内では現実には起こりえないんですけれども、仮に会派が政策立案をしたいということになった際にそういったことについては職員が公務でサポートに入ってもセーフと考えていまして、また議会基本条例にも書いてあります。ただ、公務員として携われる公務の範疇を条例に書いて拡大できるのかということについては、否定的見解を持っています。
※本記事の(下)編は2019年12月10日公開予定です(編集部)