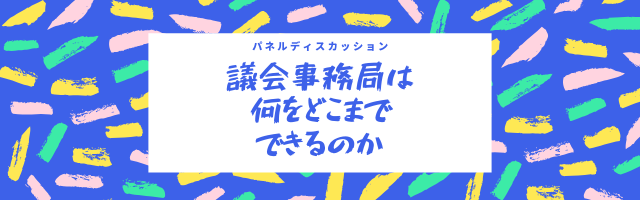「わかりにくい」議会改革をどう乗り越えるか
西川:寝屋川市議会事務局の西川と申します。議会事務局に配属になって9年目です。寝屋川市は2019年4月から中核市になりましたが、職員数は変わらず9人です。中核市の中でもかなり少ない人数かと思います。そういうこともあり、議会の改革という方向になかなか向くことができないというジレンマもあります。昨年度から議会事務局研究会に参加し学ぶ中で、このままではいけないということに気づかせていただいています。
議会改革というのは二元代表制をいかに実現していくのか、そのための手段であると思います。ただ、一般住民にとってみれば二元代表制や議会改革の意義がなかなかわかりにくい現状があります。住民の普段の暮らしの中で議会改革の意義に実感を持つということは、ほとんどないだろうというふうにも思います。
他方、もう一つの改革である「行政改革」は、成果や効果もすごくわかりやすいというのもあって進んでいるのではないかと思います。議会においても、行革的要素のある部分、たとえば議員定数や報酬、政務活動費、費用弁償の見直しなどについては取組みが進んでいるのではないでしょうか。市民にもとってもわかりやすいですし、議会自身がアピールできる面もあるのかなということが背景にあるのかなと思っています。
議会改革のわかりにくさゆえに住民から評価されることが少なく、そのために議員自身がその必要性に迫られることが少ないのではないかというふうにも思っています。さらに、議会はトップダウンの組織ではありませんので、なかなか一気呵成に物事を進めるのが難しい組織であるのかもしれません。極論ですが、議会改革の重要性というのはもしかしたら市長とか行政側に何か問題が出たときではないとなかなかわかってもらえないというところがあるかと思うんですけれども、それからでは遅いんですね。議会が機能することによって市民の生活も安定する、担保されるということでもあります。わかりにくい内容であるからこそ、それがわかっている我々議会関係者が、市民のために主体的にやっていくしかないのかなと思います。
議会事務局による委員会活動や会派活動のサポート実態は
谷畑:ありがとうございます。それぞれのお考えを、お聞きかせいただきました。議員側から見た議会改革、職員側から見た議会改革、それぞれの違いというものが見えてきたのではないかなと思います。ここからは具体的に踏み込んでまいります。現実の議会では必ずしも理想的には物事が進んでいません。むしろ、住民の側から厳しい眼で見られているところも多いかと思います。本日のシンポジウム前半の基調講演や研究報告でも、そのような問題意識を共有したかと思います。
議会の存在意義は、首長と競い合うことではありません。異なる有権者を背景に選出された議員がひとところに集まって、議論するというのが議会でして、首長はその議会が決めた範囲内で政策を遂行するのみです。

確かに首長の権限は、二元代表制の中では非常に強い側面もありますが、逆に議会の側が自らの自治立法権、自治財政権を行使して首長をがんじがらめにすることもできるのかなとも思っております。その際には議員が住民のためにいかに質の高い政策を立案・形成し、合意形成をしていくかということが非常に大事です。それが現状難しいというのは、議員の側に問題があるのか、それともサポートする側に問題があるのか、非常に課題は多いわけでありまして、議会事務局や職員の側がどれだけそれをサポートできるのかというところを突っ込んでいければと考えているところであります。
それではまずは職員側の皆さんにお話を伺いたいと思います。議会局ないしは議会事務局は、議員が委員会活動や会派活動等における調査や討議を通じて意思決定を行うための十分なサポートが果たしてできているのか。うちの議会の規模ではそこまで求められていないのではないかとか、いやうちはこれだけできていますよというようなこともあると思いますが、そういう現状やご経験も踏まえながら今後の改革の展望も含めてご意見を聞いてまいりたいというふうに思います。
まず大阪府議会の杉山さんにお聞きします。大阪府議会は先ほども全国的にもほかにないだろうということで会派活動にサポートをしているというお話もございました。その一つは委員会で色々議論をする際のサポートの仕方というところもありますし、それぞれの政党の政策というものがある中でどこまで公務員が関与していいのかという間合いというものもあろうかと思います。実際にどういうふうにこなしておられるのか、また会派拘束などがあったときに、会派間の調整というものを行わないと議会全体の合意形成がつながらないところもあろうかと思いますけれども、そういう会派間の調整や会派の政策立案へのコミット、こういったところと一般的な委員会の運営とも併せまして、大阪府議会でどういった状況にあるのかということをお願いします。
杉山:大阪府議会の場合、委員会単位での政務調査のサポートはあまりなく、基本は会派単位のサポートです。会派を担当する職員は16名で、会派比率に応じて担当職員数を決めています。これは会派間の申し合わせで決めています。現在は、大阪維新の会を担当する職員8名、自民党を担当する職員が3名、公明党を担当する職員が3名、それ以外の会派は少数会派であり担当職員は2名です。
大阪府の場合、議会が始まる前の議案説明や各政策課題等の説明を、会派単位の事前の非公開の勉強会で行っています。そのあとに正式な委員会単位での議案説明の場も設けていますが、形式的なものにとどまっています。議会前の会派勉強会の中で執行部とのやりとりが行われていて、それに基づいて執行部側は議案の修正をかけたり、議案を出すのをやめたりしている実態があり、議案が出てくるときには、方向性がほぼ固まっているというのが現状です。
議会改革については、大阪維新の会を中心にして、非常に積極的です。特に若手の議員は改革に取り組んで、それを成果として見せることが次の選挙につながるという意思がすごく大きいです。だから、わかりやすい改革が多い傾向にはあります。議員報酬や政務活動費、議員定数のカットなどです。
職員が公務員として会派のサポートに関わることについての問題意識はあります。というのも会派のサポートをする中で、会派の意思形成過程に立ち会うこととなることが少なからずあるからです。大阪府議会の中では、会派の運営や政務調査をサポートしたりすることで円滑な議会運営を図る、という考えを持って職員を携わらせています。ですから議会運営に直接の関係がない政治的な会合とかには関わってはいけません。ただ、議会の話、議会以外の話というのは必ずしも明確に切れませんので、議会運営の話がいつの間にか選挙の話になっていて、その場に職員もいるということは府議会の中では見受けられます。選挙の話になったからといってすぐに席を立つわけにはいかないので、そのまま滞在していると。その部分だけを切り取って見ると、公務員がここまで関わるのかという疑問を受けても仕方がない面もあるかもしれません。
そういう意味では、会派に法的な位置づけをするという議論もあるかと思います。特に都道府県議会のように会派単位で議会が動くような場合は、会派を上手に議会運営に取り込む方が、何らか法的な裏付けをもって取り組むことにできるようにした方が、議会も円滑に進むだろうし、府民県民にとっての議会改革につなげられるのではないかなと感じています。