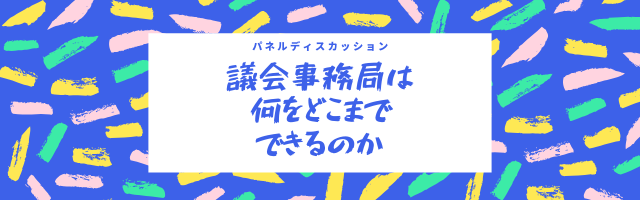地道な暮らしの中の延長線で議員活動
宮下:北海道の月形町から参りました宮下裕美子です。月形町は札幌と旭川のちょうど中間辺りに位置し、道内では比較的都市部といえます。私の町は、議会改革で有名な栗山町と同じ南空知という地区に属していますが、地理的に栗山町から少し離れていることもあって、改革は遅れており、議会基本条例もありません。横並び意識もとても強くて、議会としての改革がほとんど進んでいない状況です。
月形町は色んな意味でいわゆる町村議会の典型的な形かなと私自身は考えています。議員定数は8人で、そのうち女性議員は私1人で、月形町初の女性議員で唯一です。平均年齢については、前回の選挙で高齢の方が辞められたので60代の方がほとんどになったんですけれども、皆さん地元出身です。私は新規就農でよそから来た女性で、40歳で議員になったので、女性、若者、よそ者というすべてそろったのが私です。
私自身は、栗山町に通いながらその議会改革の在り方を学び、「ぜひこういう議会改革をやりたい。町民のために議会報告会を開き、情報公開をしたい」と、刺激を受けてきました。栗山町が積極的に取り組んでいる事柄が、すべて新鮮だったんです。というのも、私はよそ者としてうちの町に入ったときに、議会が住民に対して閉ざされているということに非常に違和感を持っていたからです。女性の地位が低く、なかなか政治に参加できないという実態もありました。まずは、そうした現状を改革したいと思って、議員活動に取り組んできました。
月形町議会事務局には、職員が2人しかいませんし、監査委員事務局も兼務していることもあり、色々なことに手を広げるのが非常に難しいです。私も条例の修正案など色々出したいのですが、事務局からのサポートは受けられない現実があります。そういうこともあって、この議会事務局研究会に入って、皆さん方にお手伝いいただきながら、こういう活動を続けています。ですから、自分の議会事務局の強化というよりは、外部の知見を活用するとか、法務能力のサポートをする議会事務局機能の広域設置ができるとよいのではと私自身は模索しています。チーム議会として、議会の機関として改革を進められるのが一番いいのですが、その前にまずは個人の議員一人ひとりの意識改革が必要だと思って、私一人でも何かできないかと思ってこういう場に参加したり、色々なスタイルを聞いて情報を得たりして、自分の議会の中で何か応用できないかと話を聞きながら、取り入れる機会を狙っているというところです。
話は変わりますが、今日辻(陽)先生の講演で、政党を中心とした改革といったお話がありましたが、私が普通の国民の立場から「政党」を見るときに、全く暮らしと直結していない印象があります。だから、暮らしの中に位置する基礎自治体からの議員活動と政党とは全然連結できないという感覚でいます。それが内と外の感覚の違い、国政というものと地方自治というものの違いなのかもしれません。政党とは全く別の次元で、地道な暮らしの中の延長線ということを感じながら、議員活動をしているところです。
議員と議会事務局がチームになること
杉山:大阪府議会事務局調査課長の杉山といいます。議会事務局研究会には初めて誘っていただきました。今日はこれまでの経験を中心にお話していきたいと思いますが、個人的な立場で来ておりまして議会を代表していませんので、あらかじめご留意いただきたいと思います。
私は議会事務局に通算12年おりまして、ずっと調査課一筋でやってきました。大阪府議会事務局には全部で3課あり、そのうちの一つが調査課です。調査課は、法務・企画グループと政務調査グループの2グループで構成されています。職員数は、調査課だけで正職員25人、非常勤3人、人材派遣8人、計36人です。
私は調査課の中でも政務調査にずっと携わってきました。大阪府議会では、会派単位に政務調査のサポートをする体制になっており、会派のサポートに関してはそれなりに色々と経験してきたかなと思っています。都道府県の中でも会派単位でサポートしているところはなかなか少ないと思いますので、課題もあるのは事実ですけれども、その辺についてお話させていただけたらと思っております。
清水:大津市議会局次長の清水と申します。私も議会局へ来まして11年です。今でこそやりがいを持って仕事をしていますが、異動当初は、職員としての裁量もないし、議会局自体が何か閉塞感に包まれているような印象を受けました。執行部であれば「前例踏襲=時代遅れ」という意識が根付いているのに、議会へ来てみると、「先例」という名のもとに「前例踏襲するのが偉い」というような感じです。しかも議員でなく、事務局職員の方が「これは議会の伝統だ」とか「議会の権威を保つためにはこうでないとだめ」という合理的でない、内向きの発想をしていると思いました。
議会改革は市民感覚とのずれを補正することだというふうに私は思っています。時代や現在の価値観からずれているところが、議会にはまだまだあると思うんですよね。執行部と比べても多いと思います。
岡田さんの発表された第二議会構想に対して、現在の議会に対する監視機関という位置づけでもいいのではという議論を実はしたんですけれども、いずれにしても、市民感覚とのずれを直すとか、市民からの議会に対する存在感を高めるという部分では、批判するだけでは市民の信頼感は高まらないと思います。だから議会は何かを生み出す必要があって、それはやっぱり政策です。そして政策を生み出すときに重要なのは、議員と議会局の職員がチームになって作り出す、ということです。つまり、「チーム議会」を成立させるということが大事だと、最近はそう思って仕事をしています。