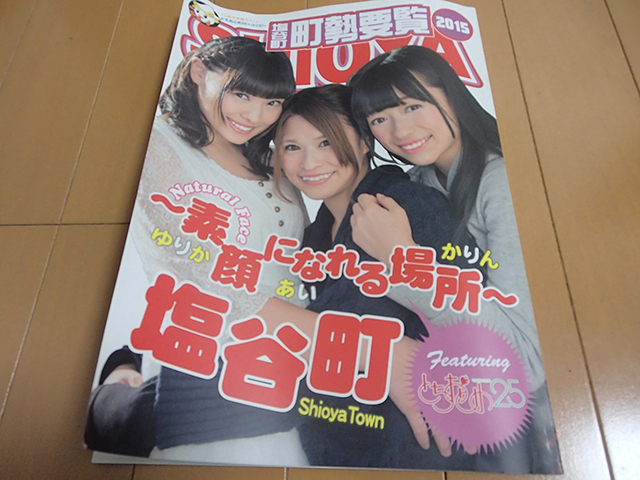2018.01.25 政策研究
第1回 ネット活用の町民全員会議で町を活性化
全国初の町民全員会議スタート
こうした経緯を経た上で、2015年10月27日に第1回目の「塩谷町民全員会議」が始まった。会議のテーマは「塩谷町への気付きの時」。中学生以上の町民全員にIDとパスワードが配布され、同時に回答専用用紙も配布された。参加者はパソコンとスマートフォン組が約300人。専用用紙による参加の方が圧倒的に多く、合計2,309人に上った。複数回答や無回答などを除外した有効回答は1,995人(町議12人を含む)となり、全ての町民まではいかなかったものの町民の6人に1人が町の新たな取組みに参加したのである。
町民全員会議で町民に示された設問は9つ。最初の問いかけは「現在の塩谷町の活気が以前よりも増していると思いますか?」というものだった。参考情報として添付されたのが、町の人口がここ5年間で861人減少していること。そして、出生数が年平均67人で、人口1,000人当たり5.3人になり、全国1,741市区町村の中で1,474番目ということも示された。この設問に対し、「低下している」との回答は88%に上った。
また、「塩谷町の住民が日常的に使う(買い物などに使われる)お金の多くが塩谷町の外に流出している状況を知っていましたか?」という設問も。ここでも客観的なデータが添付されており、住民に町の現状を再確認させる意味を持っていた。データによると、塩谷町の住民が買い物で使うお金の多くは矢板市内で39%、次いで日光市内が19%、宇都宮市内が16%となり、地元での買い物はわずか15%であった。回答した町民の84%がこうした町外への富の流出を知っていたと答えたが、具体的な数値を知らされて驚いたのではないか。
町への定住意向を問う設問もあった。全体の77%がこれからも住み続ける(住み続けるしかないとの消極的な意向も含む)と答えたが、その数値は年齢とともに低下していた。20代の53%が非定住意向で、10代は71%。30代に「わからない」と回答した人が多いのが特徴的だった。
こうした設問への回答を見ると、住民の多くが人口流出や経済的な衰退といった町の厳しい現状を認識していたことが分かる。では、住民はどうしたらよいか、どうすべきと考えているのか。町民全員会議での全回答を基に、住民個々の考えや意思を分析し、タイプ分けした。その結果、人が育つまちづくりで転出を防ぐ考え方が20.7%と最も多く、人が育つまちづくりで転入を促進するが18.5%、産業振興で転出を防ぐという考え方が18.2%となった。塩谷町の住民ニーズは「人が育つまちづくり」であることが明らかになった。
町民全員会議の実現に奮闘した当時の担当者、星さんは「行政が住民の満足度を考えずに自己満足的に施策を進めるケースが多い。そうではなくて、住民の意見をしっかり把握し、きちんと吸い上げて施策を進めていくように変えたい。そのためには住民とのコミュニケーションツールをどうつくるかがポイントとなります。特に若い方たちです。まずは彼らとネットでつながっていきたいと思いまして、その仕組みをつくりました。互いに(情報や意見、考え方の)キャッチボールを行い、実際に顏も合わせて話し合い、さらには行動にもつなげたい」と、町民全員会議の意義や狙いを熱く語った。
どう生かし進化させるか
しかし、町民全員会議は課題点も抱えていた。ひとつは、住民の関心度が高くないという点だ。「若い人だけを集めた説明会の開催を計画したが、実施できずにいる」(星さんの話)。また、インターネットになじみのない住民は内容がよく分からず、「何やら不思議なものに見えているようだ」(ある町民の指摘)という実態もある。
さらにもう1点、町民全員会議で示される住民の意見や提言などを具体的な施策に落とし込むまでには至っていないことも挙げられる。行政の縦割りの弊害や職員の意識や熱意のバラツキ、さらには議会の関わり方が不明確な点なども影響しているようだ。ちなみに塩谷町議会は定数12人で、全員男性。60代が7人、70代が2人、50代が2人、40代が1人で、インターネットを活用しない議員がほとんどだという。そうした事情もあってか「今まで町議会で町民全員会議のことが取り上げられたことはありません」(橋本巌議員の話)という。議員の中には町民全員会議の取組みを高く評価する人もいるが、よく分からないというのが大勢のようだ。議会が町民全員会議とどのように連携するかといった視点や発想、戦略が乏しいのである。
そうはいっても塩谷町の取組みは日本の自治体で初めてのこと。試行錯誤せざるを得ないのはある意味、当然といえる。町は1回目の町民全員会議後の2017年1月、町の中学生全員(266人)にアンケート調査を実施した。町の将来を担う若年層の声をしっかり聞く必要があると考え、定住意向や町への好感度、町に応援してもらいたいことなどを改めて尋ねたのである。町はさらに2回目の町民全員会議の開催を2017年度中に計画している。予定しているテーマは「人が育つ塩谷町へ」である。
自治の担い手を目指す動き
こうした塩谷町の真摯な取組みに呼応する動きが町内に生まれている。自分たちが中心になってまちづくりを進めようという新たな動きだ。町の商工会青年部(OBを含む)やJA青年部のメンバーらで、主に子育て世代の30代である。
「先輩たちがもっと頑張ってくれと思っていましたが、俺ら世代が頑張らなければ、ダメだと思うようになりました。行政頼みや議員頼みはやめ、1人ひとりが地域のために考え、行動しなければダメです。もう他人のせいにしてはいけない。1人ひとりがしっかり情報を得て、自分でものを考えていく。そういう人が増えれば、地域は必ず強くなると思います。痛い目に遭って初めて気づきました」
こう語るのは、塩谷町内で酒造会社を経営する小嶋拓さん。商工会青年部の部長経験者である。
37歳の小嶋さんは、20年後の地域を見据えて今から自分たちが行動しなければ、地域の未来はないと切実に語る。すでに同世代の仲間たちとまちづくりや子育て、教育などについて話合いを重ね、その輪を広げつつあるという。そうした仲間たちと連携し、まちづくりのための行動に出たいと力強く語る。
手探り状態で始まった塩谷町の町民全員会議は、自治の担い手を再生させる力を内在させたものといえよう。成果を性急に求めず、試行錯誤を重ねながら粘り強く続けていけば、自治の担い手の再生と地域の活性化にたどり着くことができるのではないだろうか。