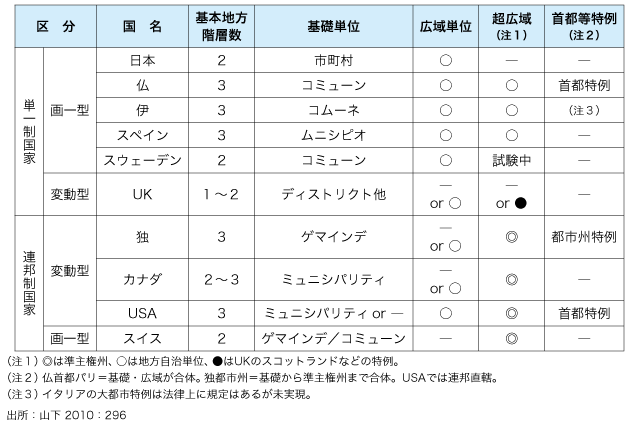2016.12.26 議会改革
第7回 地方自治の二層制の変化と住民自治(下)――議会改革を多層な自治の住民統制に活かす――
① 「都」構想をめぐる動向
「大阪都」構想を実現する法律が制定された(大都市地域における特別区の設置に関する法律、2012年8月)。この法律は、市を廃止して特別区を設置するためのいわゆる手続法である。その内容は、以下のとおりである。当該市町村(単独及び周辺地域を含めて200万人以上)及び当該道府県のそれぞれの議会の議決、特別区設置協議会の設置、総務大臣との協議、特別区設置協定書の作成、当該自治体(道府県及び市町村)すべての議会の承認、特別区設置協定書の公表、当該市町村の選挙人の投票、それぞれ過半数の賛成、当該自治体及び道府県による共同申請、総務大臣による市町村廃止・特別区設置の処分・告示、である。「大阪都」構想を目指す運動の過程で制定された法律であったが、大阪府だけを対象とする特別法ではなく、その他の自治体にも適用できる一般法として制定された(5党(7会派)による法案提出)。
「大阪都」構想は、当初地制調の審議の対象となることが想定されていた(第30次地制調第7回専門小委員会(2012年2月16日)での橋下徹大阪市長のヒヤリング等参照)。それが現実政治の中で、「大阪都」構想は法律として制定された。地制調はこれを正面から審議するのではなく、当該法律に即しながら留意点を提示するという限定的なものへとシフトしている。東京都の特別区の自治権拡充運動を踏まえて、「自治」(財政調整制度、職員の身分(都職員の特別区配属制の問題性)、住民自治など)の視点からの留意点は、制度改革にとっては重要な論点である。
「大阪都」構想をめぐって、2015年に住民投票が行われたが、僅差で実現には至らなかった。
② 特別自治市構想をめぐる動向
指定都市市長会が特別自治市構想を掲げている。特別自治市は都道府県から独立し一層制の自治体となることによって、都道府県と市町村の事務を一括処理することになる。それは、「二重行政」を解消して「効率的効果的な行政体制整備」に資する。第30次地制調でも議論された。新たな大都市制度である特別自治市を設置することについては、指定都市への事務と税財源の移譲を「可能な限り進め、実質的に特別市(仮称)(=特別自治市――引用者注)に近づけることを目指すこと」と踏み込んでいるが、引き続きの「検討」の域を出ない。
特別自治市の構図と一致している特別市は、地方自治法制定時にすでに規定されていた(第3編第1章第1節 特別市(264-280)(昭和31年法律147号により削除))。
特別市は、都道府県と市の事務を担う(都道府県から独立)。人口50万人以上の市について、区は行政区として、「行政区に区長及び区助役一人を置く」が、区長は公選、助役は事務吏員の中から市長が命じる(昭和31年法律147号改正前自治法271)。特別市は、法律で定める。なお、特別市の指定のための特別法は住民投票(憲法95)に当たると解釈され、「関係都道府県の選挙人の賛否の投票に付さなければならない」(昭和31年法律147号改正前自治法265⑨)(3)。
特別市・特別自治市が、実現には至らなかった、あるいは検討の域を出ないのは、次のことに応えられないからである。
ⅰ 警察事務が都道府県と特別自治市に分割され、「組織犯罪等の広域犯罪への対応」の懸念。
ⅱ 道府県税、市町村税を一括賦課徴収することによる「周辺自治体に対する都道府県の行政サービス提供への影響」の懸念(4)。
ⅲ 特別自治市内の「区」に対する住民代表機能の整備の懸念。
ⅳ 現行の指定都市は多様であり、一括特別自治市とすることへの懸念(例えば、人口200万人以上というように限定)。
こうした問題を是正しない限り、特別自治市構想は進展しない。指定都市は、団体自治問題(道府県と指定都市との関係)だけではなく、住民自治問題(行政区には議会が設置されていない)がある。横浜市、名古屋市、大阪市など「巨大都市の下部機構が現行の行政区のままであって良いのか」検討すべき時期に来ている(西尾 2013a:195)(5)。
筆者は特別自治市構想における住民自治の軽視が、地制調での特別自治市構想の消極姿勢を招いた要因の1つだと考えている。特別自治市の「区」の議会設置、公選制に対する消極姿勢である。特別自治市を説明していた林文子横浜市長、阿部孝夫川崎市長(当時)に対し、同席していた橋下徹大阪市長(当時)は、最初は軌を一にした改革と賛同していたが、林、阿部両市長の「区」の公選制に対する消極姿勢に対して強い批判をしていた(第30次地制調第7回専門小委員会(2012年2月16日)(江藤 2013))。「区」に公選の長、議会を設置して二層制を制度化すべきとはいえないが、「少なくとも、過去の特別市制度に公選の区長が存在していたように、何らかの住民代表機能を持つ区が必要である」(第30次地制調答申)。