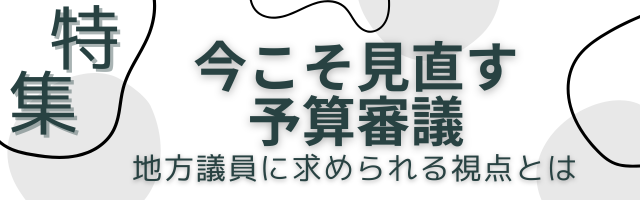1 静かに広がる閉塞感
2025年は「地方分権一括法」の施行から四半世紀、「まち・ひと・しごと創生法」の施行から10年が経過した年に当たる。地方に権限が移譲され、地方創生にも取り組んできたこの25年間、皆さんがお住まいの地域は、以前と比べてどのように変化してきただろうか?
筆者は、全国各地の市町村役場を訪問し、首長や議員、職員の皆さんの話を聞くことが多い。その際、共通点として次のような事項を耳にする。
【地域の問題】
・買物をする場所が少なくなっている(なくなった)
・公共交通が縮小・廃止している
・近所にあった診療所(病院)がなくなった
・ハローワークの有効求人倍率は高いが地元企業では従事者不足が続いている
・高校を卒業し大学進学や就職で地域外へ出たら戻ってこない
・空き家が増えている
・休耕田が増えている
・一人暮らしの高齢者が増えている
・認知症患者が増えている
・消防団員、民生委員、保護司などのなり手不足が深刻化している
・自治会役員のなり手不足が深刻化している
・地元の祭りやイベントが形骸化し費用対効果が薄い
・小中高校等の統廃合が必要な状況になっている
・上下水道の維持管理(公共施設の維持管理・統合)が厳しさを増している
・地元産業の後継者不足が深刻化している
都市部から距離のある市町村の場合が多いが、都市部であっても空き家の増加や認知症患者の増加、消防団員等のなり手不足等々、これらの問題を抱えている自治体は多数存在している。そして、こうした地域の問題を縮小したり解決する活動の核となっているのが役所であるが、その役所の中にも様々な問題が発生している。
【役所内の問題】
・若手職員が辞めていく
・休職者が増加している
・早期退職希望者が増加している
・管理職のなり手不足が深刻化している
・公務員希望者が減少している
・職員に余裕のない職場風土が改善されない
・なくならない事務処理ミス
・明らかに職員数が足りず一人がキャパを超える事業を担当している
・組織が縦割りで部署を超えた連携が生まれにくい
・管理職がプレイヤーのままで組織に統一感が生まれない
・職員が日々頑張っているのに成果が出ない政策
・絵に描いた餅状態の総合計画
・職員研修を重ねても育たない人材
・打ち破れない組織の慣例
・人事担当者しか知らない人材育成基本方針
このように、地域の問題解決に行政職員の皆さんも日々努力を重ねているのだが、明快な打開策を見つけられず、地域や役所内には閉塞感がジワジワと広がっているように感じるのは筆者だけだろうか?