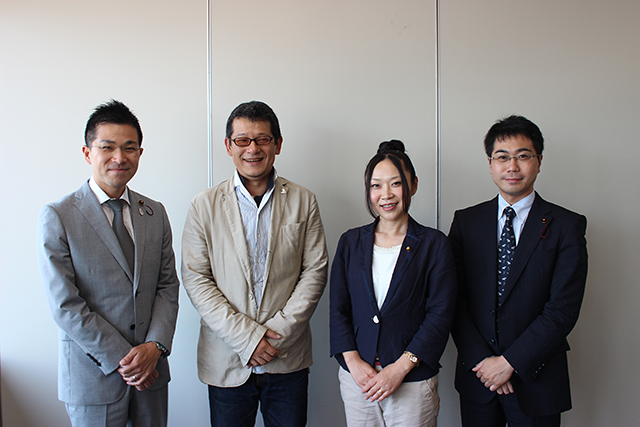統一地方選を勝ち抜いた子育て世代の3人の新人議員が、初議会を終えて感じた疑問や、これからの活動への不安を、ざっくばらんに先輩に相談してみました。未来を担うフレッシュな議員ならではの「あるある体験」に議会の先達が、エールとアドバイスを送ります!(※本記事は2015年8月25日掲載記事の再掲です)
出席者
【4月当選新人議員】
〇荻野健司さん(世田谷区議会議員)
〇近藤美保さん(流山市議会議員)
〇三雲崇正さん(新宿区議会議員)
【アドバイザー】
〇松野豊さん(前・流山市議会議員/麗澤大学地域連携センター客員研究員)
初めてづくしの質問、答弁(荻野)
松野 人生初の議会の感想を聞かせてください。
荻野 やっぱり一般質問が大変でした。これまで議会を傍聴したこともあり、本会議場の雰囲気だとか、答弁のやり方は何となく分かっていたのですが、そこに至る過程で、いろいろ苦労があるのだなということがよく分かりました。特に我々新人の場合、当選から1か月ですぐ質問をつくらなくてはならなかったので、とにかく質問を考えて、それから担当部署の方がヒアリングに来てと、何も分からないまま一通り経験してみたといったところです。何しろ質問の順番も二番手だったためか傍聴も多く、選挙より緊張しました。
近藤 私のいる会派は、8人中5人が新人です。さっそく教育福祉委員会で討論の機会がありました。流山市の6月議会では、福祉手当の廃止(1)が議論されました。過去の文献なども全部読み込み、担当部署に十分なヒアリングもして、私としては確信を持って「廃止」と判断して討論したのですが、反対派からヤジを受けびっくりしました。
先輩からのアドバイス【ヤジがあっても大丈夫!】
![]() ヤジといえば、昨年6月に東京都議会で品のないヤジが飛んだことがメディアで話題になりましたが、そもそも「野次」の語源は「野次馬」で、「自分とは無関係なことに口を出す人」、「他人に便乗して無責任に騒ぎ立てる人」という意味です。一方で歌舞伎などでは「成田屋!」、「中村屋!」といったかけ声で、贔屓(ひいき)の役者に声援を送る文化もあります。同様に、議会のヤジにもいろいろあって、エールを送るものや、場を盛り上げるものがあるのです。様々な議論をするのが言論の府である議会の使命です。物事の正解はひとつではありませんし、ヤジがあったからといっておびえるのではなく、正々堂々とご自身の意見を主張されたらよいと思います。ただし、議題と関係のないヤジや誹謗(ひぼう)中傷に当たるようなヤジが飛んできた場合は、いったん深呼吸をして心を落ち着かせ、議長(委員長)に審議の休憩を申し入れ、注意をしてもらうようにしましょう。(松野)
ヤジといえば、昨年6月に東京都議会で品のないヤジが飛んだことがメディアで話題になりましたが、そもそも「野次」の語源は「野次馬」で、「自分とは無関係なことに口を出す人」、「他人に便乗して無責任に騒ぎ立てる人」という意味です。一方で歌舞伎などでは「成田屋!」、「中村屋!」といったかけ声で、贔屓(ひいき)の役者に声援を送る文化もあります。同様に、議会のヤジにもいろいろあって、エールを送るものや、場を盛り上げるものがあるのです。様々な議論をするのが言論の府である議会の使命です。物事の正解はひとつではありませんし、ヤジがあったからといっておびえるのではなく、正々堂々とご自身の意見を主張されたらよいと思います。ただし、議題と関係のないヤジや誹謗(ひぼう)中傷に当たるようなヤジが飛んできた場合は、いったん深呼吸をして心を落ち着かせ、議長(委員長)に審議の休憩を申し入れ、注意をしてもらうようにしましょう。(松野)  松野豊さん
松野豊さん
近藤 でも、議員同士の討論ではバチバチっと火花を散らしていても、終わった後は皆さんフランクで、冗談なんか言い合ったりして、この頭の切り替えもすごいなと思いました。私も議会の傍聴をしたことがあったのですが、そういう論戦場面を外から見ていたときには、この議員とあの議員は敵対しているから、足の引っ張り合いをしているのだと思っていました。外から見ているのとは、ちょっと違う。
先輩からのアドバイス【議会の外からは分からない、議員同士の「よい関係」とは?】
![]() 議会に限らず、中に入ってみないと、あるいは中に入ってもすぐには分からないことというのは、たくさんあるのではないでしょうか。例えば、夫婦や恋人同士の関係は当事者にしか理解できないものです。議員というのは支援者(地域や業界団体など)によって支えられていますし、所属政党の有無やイデオロギーなどによっても考え方は、それぞれです。とはいえ「自分の住んでいる街を、よりよくしよう!」という思いでつながっているものです。主義主張や方法論が違っていても「ひとつになれる」ということを信じて、相手を信頼し、自分自身も相手から信頼されるような言動を積み重ねて、成果を出していくことができれば、議員同士でもよい人間関係を築くことができるはずです。(松野)
議会に限らず、中に入ってみないと、あるいは中に入ってもすぐには分からないことというのは、たくさんあるのではないでしょうか。例えば、夫婦や恋人同士の関係は当事者にしか理解できないものです。議員というのは支援者(地域や業界団体など)によって支えられていますし、所属政党の有無やイデオロギーなどによっても考え方は、それぞれです。とはいえ「自分の住んでいる街を、よりよくしよう!」という思いでつながっているものです。主義主張や方法論が違っていても「ひとつになれる」ということを信じて、相手を信頼し、自分自身も相手から信頼されるような言動を積み重ねて、成果を出していくことができれば、議員同士でもよい人間関係を築くことができるはずです。(松野)
松野 三雲さんは弁護士でもありますが、議員業とのギャップはありますか。
三雲 弁護士の仕事というのは、依頼者の権利擁護が第一で、とにかく相手方と交渉して利益を最大化するという、そのために頑張ることが仕事ですけれども、議員がそれをやり切ってしまうと、全体のバランスが悪くなる可能性もある。そこは一歩引いたところで、区全体あるいは地域全体にとって、どうするのがベストかという視点で考え、解決しなくてはなりません。
例えば、地域の方から「こういうことをしてほしい」、「ここに問題がある」とお話を聞いて、そのとおりだとアクションを起こそうという段階で、実はその件はすでに話し合われており、決着していたということもあり得るわけです。いろいろ制度的な問題があって手が出せなくなっている案件などもあり、バランスを考えながら議論を進める必要もあります。
また、当然ですが委員会は、出てくる案件がそれぞれの地域の話だということですね。地域ごとに議員がいるので、その議員の手前、あまり勝手なことを言ってはいけないなと感じました。同じ会派にその地域の人がいたら、事前に「そちらに陳情が届いていますか?」と聞きながら発言をするという感じでした。
先輩からのアドバイス【議員に求められるバランス感覚って?】
![]() 私も議員になりたての頃は、周囲に気を使っていました。一定の社会経験を積まれてから議員になった方々は協調性を重んじるため、バランスを考えがちですが、議会では自分の主張を相手にハッキリと伝えないと、成果を出すことは困難です。公務員と同じ発想でバランスをとることばかり考えていては、何もしないのがベターという結果になるからです。相手の立場や主張も理解することが前提ですが、「でも私はこのように考える。なぜなら◯◯だからだ!」という主張をすることが、議員に求められるスタンスだと私は思います。(松野)
私も議員になりたての頃は、周囲に気を使っていました。一定の社会経験を積まれてから議員になった方々は協調性を重んじるため、バランスを考えがちですが、議会では自分の主張を相手にハッキリと伝えないと、成果を出すことは困難です。公務員と同じ発想でバランスをとることばかり考えていては、何もしないのがベターという結果になるからです。相手の立場や主張も理解することが前提ですが、「でも私はこのように考える。なぜなら◯◯だからだ!」という主張をすることが、議員に求められるスタンスだと私は思います。(松野)