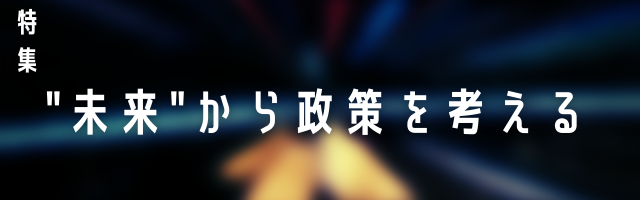
フューチャー・デザイン:「今」の世代と「将来」の世代の幸せのために
総合地球環境学研究所・高知工科大学フューチャー・デザイン研究所 西條辰義
フューチャー・デザインのバックグラウンド
少子高齢化、社会インフラの老朽化などが進行する一方、公的な財政も逼迫(ひっぱく)し、将来、私たちは従来のようなサービスを受けることができなくなるかもしれません。そのため、市民の皆さんと行政が対立することもあるでしょう。市町村の合併のため、例えば同じ地域に複数のスポーツ施設や福祉施設があるとしても、そのうちいくつかを畳むことは容易ではありません。新たな施設などもってのほかです。さらには、近隣の市町村と施設などの集約化を目指しても、なかなか合意には至らないのが常です。
日本発の「フューチャー・デザイン(以下「FD」という)」という新たな研究分野で分かってきたことは、「今」から「将来」に向けての議論では、どうも「今」に足が絡んでしまい、参加者の皆さんの思いの向きが異なるため、問題の解決に向けたアイデアが出にくいことです。一方で、参加者の皆さんが「将来」に飛び、そこでの社会を描き、そこから「今」何をすべきかを考えると、独創的なアイデアを提案し始めるのです。加えて、将来に飛んだ「仮想将来人」は、「今」と「将来」の両方を高い位置から鳥瞰(ちょうかん)するようになり、皆さんの間での対立が起こりにくいことも分かっています。
矢巾町のフューチャー・デザイン
まず、世界で初めてFDを採用した岩手県矢巾町の事例を紹介しましょう。矢巾町は県都・盛岡市のすぐ南に位置する田園風景が残っているのどかな町で、人口は約2万7,000人です。2015年、内閣府の要請により、2060年に向けて各市町村が「長期ビジョン」を作成することになったため、半年かけて町はコンサルタントにそれをお願いするとともに、町民の皆さんと一緒にFDでビジョンをつくることにしたのです。5人程度の二つのグループには、「今」から2060年の矢巾町をイメージし、そこから今の政策を考えてもらいました。一方で別の二つのグループには、タイムマシーンで2060年に飛び、そこから「今」の政策を考えてもらったのです。
今から将来を考えたグループは、2060年になっても待機児童がいるのは困る、老人介護施設が少ないのも困るなどという今の課題を将来の課題に置き換えてしまったのです。一方、仮想将来世代(2060年から今を考えたグループ)は、町の交通体系、医療体制など、高い視点から様々な提案をしたのです。一つ例を紹介しましょう。町には南昌山というおむすび型の山があります。実は、この山の頂上には銀河鉄道の出発駅があったのだそうです。宮沢賢治がこの山に何度も登り、ここであの美しい『銀河鉄道の夜』を創作したということが町の人々の誇りです。そこで銀河鉄道を主題とする自然公園に南昌山を変えるのだ、というタイプの提案が数多く出たのです。
この様子を眺めていたのが高橋昌造町長です。彼は、2018年度の施政方針演説で、矢巾町は「フューチャー・デザイン・タウン」であることを宣言し、2019年の4月には、将来課に相当する未来戦略室を立ち上げました。未来戦略室は、半年がかりで、住民の皆さんとともに、FDを用いて町の総合計画を考えたのです。何と、FD提案の83%が総合計画の最終案に採用されました。また、プールなどの新たな施設をつくるのではなく、住民の健康を運動で支える「ウェルネス・タウン」構想を実現しているのです。
従来、矢巾町では総合計画を策定する際、町のステークホルダーによって構成される60人委員会がその任を負っていました。実は、今回も60人委員会と並行して、FD実践が行われており、60人委員会の何人かはFDにも参加していたのです。その人たちは、FDを経験し、「60人委員会で町の将来が描けるわけがない」と思ったのだそうです。FDでは「将来」から「今」を見ることのみならず、4人程度のグループでしっかりと議論をします。2時間の60人委員会なら1人当たりの発言時間は2分です。これではよいビジョンができるわけがありません。実際は、裏方の皆さんがつくっているのです。








