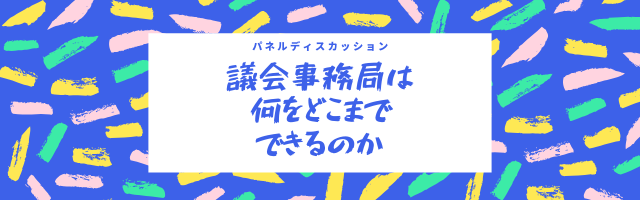2019年8月31日(土)、大阪大学中之島センターにおいて「今、改めて議会の存在意義を問う~二元代表制の空洞化への懸念から~」と題したシンポジウムが開催されました。これは、西日本を中心として活動してきた「議会事務局研究会」の設立10周年記念で企画されたものです。シンポジウムの中から、パネルディスカッションを中心に以下ご紹介します(※本記事の(上)はこちら)。

<コーディネーター>
湖南市長 谷畑英吾さん
<パネリスト>
兵庫県西脇市市議会議長 林晴信さん
北海道月形町議会議員 宮下裕美子さん
大阪府議会事務局 杉山智博さん
滋賀県大津市議会議会局 清水克士さん
大阪府寝屋川市議会事務局 西川明広さん
議長の人事権
谷畑:ありがとうございました。本日お越しの林議長と宮下議員の所属される議会は、ここまでお話いただいた皆さんの議会に比べれば、規模の小さい議会に分類されるわけであります。しかし、規模が小さくとも議会の審議内容や意思決定の質の向上のためにこれまでも色々と工夫されてきたと思います。高沖(秀宣)さんの報告の中でも小規模自治体議会ほど改革が進んでいるケースもあるというお話がありました。しかし、果たしてそれがどこまで制度的に担保されているものなのか。たまたまそこに素晴らしい議員、そして事務局職員がいて、努力でできているだけなのか、そこには持続可能性の課題などもあるかと思います。
ここまでのディスカッションで、比較的大きな自治体規模における議会運営のお話をお聞きしてきましたが、ここからは事務局体制が必ずしも整っていない中で、審議機能の充実や政策立案のサポート体制の充実をどうはかれるか、議員として何ができるのか、できないのか、課題整理をお願いしたいと思います。
たとえば事務局人事について議長の人事権はどう担保できるのでしょうか。議会事務局体制の充実にはどう取り組んだらよいのでしょうか。近隣の事務局と共同設置というのもありうると思
います。また、会派制まで取れない場合は、議員間での自由討論をどういうふうに確保していくのかというようなことについても、小規模自治体ならではの悩みもあると思いますので、そういった点について林議長からよろしくお願いいたします。
林:まず、議長の人事権については、「議長の許可なく勝手な人事は許さない」ということを総務部長に常に伝えています。私が議長になりたてのときに、ある日事務局長から「事務局の○○が替わります」という報告を受けました。従来そういうふうに事後報告でやってきたと思うんですが、私はすぐに総務部長を呼び、「人事権は誰にあると思っているのか」と尋ねました。「なぜ事務局長から私が報告を受けなければならないのか」、「まず議長に対して相談があるべきではないか」ということを申しましたら、ご理解をいただけたようで、それ以降の人事異動では、まず総務部長や副市長が来られて、議長に対する確認をきっちり行ってくれるようになりました。議長の許可を得て、事務局人事をしてくれるようにはなったということです。ただ、私もすべての職員を知っているわけではないので、職員を替える場合は事務局長と必ず相談するようにしています。
議会事務局の共同設置については、政策立案等の機能については共同で担えるとありがたいと思っております。一方で、議事等については議会それぞれのやり方もありますし、委員長等も必ず事務局長等と相談しながら議事を進めているようなところがありますので、気軽に相談できる体制整備という面から考えると、共同化は難しいのではないかと。このように、議会事務局の機能すべてを共同設置でというのは難しいと思っております。
議会事務局の関わり方
林:また、議会の意思決定に議会事務局がどこまで関われるかということについてですが、「事務局がこう言ったから私の決定を変えます」というような議員はいらないと私は思います。ただ、議会事務局が様々な情報を整理して、議員や会派に正確に伝えるということ自体は大事だろうと。おそらく当局側が説明するより、事務局が説明するほうが、より身近な存在っていうのもあるのでしょうが、わかりやすい部分はあると思っています。西脇市議会では、事務局長が議案の説明を作成し、議員に渡しています。簡単に言うとこの議案はこういうことですよというのを、それを読んで把握したうえで、議案説明を受け、それから委員会を開いて、委員会で資料請求について議員間討議をして決めるという流れです。
定例会が始まりますと、委員会が始まる前に、委員同士で集まって、「今回はどんな質問をするか?」ということを一人ひとりに聞きます。そして「私こんな質問しようと思っています」、「それを質問するなら、こんな論点があるのでは」などとやり取りをします。そうやって、色々なことを議員同士で話し合うのです。すべての質問がそういったプロセスにのるわけではありませんが、「委員会としてどういう質問をするか」、「この議案のポイントは何か」など、本番の委員会が始まる前の段階で委員間討議を行うというわけです。この取組みは、元々は予算・決算の審査の際に始めたのですが、通常の条例改正や条例の新設などにも広げています。つい昨日も「議案の新設の場合にはこういう点をチェックしよう」といった話もしたところです。他にも、「他の自治体の条例を単純に引っ張ってくるとこんな課題がある」とか「審議会の議事録はすべて読もう」、「パブリックコメントではどんな意見が出ていたのか確認しよう」といったことを、事務局も交えて話し合いしています。こういった議論は本番の委員会審議に生かしていくことになりますし、だからこそ議会事務局は関わってくれています。
西脇市議会では、条例や規約を作るときには、たたき台は議員が作るのですが、そのあとには議会事務局が当局と調整して進めてくれます。それは非常にサポートとしてありがたく思っています。ただ、大規模自治体議会の調査結果を高沖さんから聞いた折に、たしか福岡市議会では議員が「こういう風な政策提案をしたい、条例を作りたい」って言うと、それを全部条例にしてくれる担当がいるそうです。これは衆議院法制局に勤められた方からのお話を聞いたときも感じたのですが、やっぱり大きい議会にはすごいシステムがあると思います。しかし、では何故もっと条例含め政策提案をしないだろうかとも思います。そんなシステムがあるのであれば、年間に2本とか3本でなく、10本、20本できるのではないかと。条例案を可決する、しないというのは別にしても、大きな議会はもっと政策提案をやっていけばいいし、我々くらいの自治体規模でしたら年に1本ないし、任期で1本くらいは条例の提案ができるような形に持っていきたい。そのための議会づくりを、事務局と一緒になってやっていきたいと思っているところです。