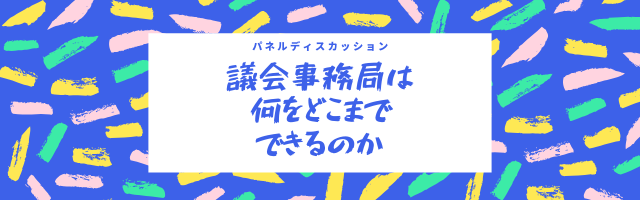2019年8月31日(土)、大阪大学中之島センターにおいて「今、改めて議会の存在意義を問う~二元代表制の空洞化への懸念から~」と題したシンポジウムが開催されました。これは、西日本を中心として活動してきた「議会事務局研究会」の設立10周年記念で企画されたものです。シンポジウムの中から、パネルディスカッションを中心に以下ご紹介します。

<コーディネーター>
湖南市長 谷畑英吾さん
<パネリスト>
兵庫県西脇市市議会議長 林晴信さん
北海道月形町議会議員 宮下裕美子さん
大阪府議会事務局 杉山智博さん
滋賀県大津市議会議会局 清水克士さん
大阪府寝屋川市議会事務局 西川明広さん
議会事務局は何をどこまでできるのか
谷畑:本日のシンポジウムは「議会の存在意義を問う」という非常に刺激的なテーマを掲げています。そのパネルディスカッションのコーディネーターが、果たして首長でよいのかという疑問はありますが、面白ければいいだろうということでご容赦いただきまして、議会事務局研究会会員として政治的に偏ることなく、皆さまと真実を探求していけたらと思っています。
本日シンポジウム前半のご発表は大要、議会改革は画一的なものではなく、多様性を制度的に認める必要性があるという主張だったかと思います。歴史を遡れば、我が国の議会制度は明治期に府県制、市制町村制など規模によって当初は差異がある中でスタートし、法制的には昭和18年頃までには統一化され、さらに戦後、地方自治法によって画一化されたという経緯があります。しかし、実際のところ、全国どこの議会を見ても、全く同じという議会はありません。
これから始まるパネルディスカッションでは、そうした多様な改革を求められる地方議会において、議会事務局は何をどこまでできるのか、について議論を深めていきたいと考えています。地方分権改革から20年が経とうする現在、改めて、地方議会とはなんなのか、議会改革は誰のために行うのか、議会における意思決定の質や政策立案、形成機能はどうすれば高めていくことができるのか、そこに議会局職員はどのように関わっていけばよいのか、など検討してまいります。
また、本日は議会の規模に起因する多様性あるいは共通点を確認するとともに、議会を構成する議員と事務局職員の立場の違いも考えていければと思います。
人口41,000人の兵庫県西脇市議会から林晴信議長、人口3,000人の北海道月形町議会から宮下裕美子議員にご参加いただいています。また議会局職員として、人口882万人の広域自治体である大阪府議会事務局から杉山智博調査課長、そして人口34万4,000人の中核市である大津市議会局から清水克士議会局次長、さらには人口23万3,000人の寝屋川市議会事務局から西川明広課長にご出席をいただきました。
議会事務局の規模は、大阪府は65人、大津市は17人、寝屋川市は9人、西脇市は6人、月形町は2人と、千差万別です。もともと議会事務局は、歴史的には書記の事務からスタートして、議事を中心に回すことが主な事務でした。その後、庶務から事務に変わり、そして近年では政策形成にもコミットするようになり、仕事のバリエーションも、時代とともに変わってきました。本日のディスカッションでは、多様性のある現状と課題を共有し、画一的な制度に縛られるべきかどうかという問題意識が芽生えれば成功かなと思っているところです。
それでは最初に皆さんからの自己紹介を兼ね、先ほどの基調講演、研究報告の感想、また皆さんが思い描く議会改革やその理想について、一人4分程度でお話をお願いします。
議会は住民の中にある
林:西脇市議会議長の林です。今日の講演は刺激的な内容が盛り沢山でした。特に岡田(博史)さんが発表された「第二議会構想」に衝撃を覚えた方もいたのではないでしょうか。議会事務局研究会としては第二議会構想の発想が面白いということで、興味をもって議論をしてきました。しかし、よく考えてみると、こういった構想が出てくるということは、少なくとも岡田さんは現状の議会改革に失望をしているのかもしれません。これに対して、私たち議会人としては忸怩たる思いを持たねばなりませんし、ますます真剣に改革に取り組んでいかなければなりません。
ところで、岡田さんが第二議会構想の中で掲げた、たとえばSNSやワークショップを使った住民意見の集約は、現行制度の中でもできます。やっていないだけです。なんでやらないのか。「できない」のか、「やらない」のかというのは、非常に大きな問題であろうなと思っています。
私が考える、議会改革で一番大事なことというのは、「議会は住民の中にあるということを常に心がけること」です。議会や市の制度を説明するときによく三角形を描きますね。その三角の頂点がそれぞれ「住民」、「議会」、「行政(市長)」です。しかし、私はそのたとえは間違いだと思っています。本当は、まず丸を書いて「住民」、その中に「議会」という丸を書いて、そこから線を引っ張って「市長(行政)」と書くべきです。なぜなら、議場はその構成になっていますよね。執行部がいて、議員がいてその周りを傍聴者(住民)がぐるりと囲んでいて、対峙する形になっています。これが正しい制度説明と思っています。
ただし、住民の中には、ひょっとしたら議員の中にも、「行政の中に議会があって住民がある」と思っている方がいるかもしれません。それも、市役所の建物の中に議会棟がある、そのことだけで行政=議会とイメージしている。これがまず不幸の始まりだと思っています。そうではなく、住民の中に議会がある、ということをいかに住民に理解してもらうかということが、議会改革であると思っています。
さらに、住民の様々な意見を多様なチャンネルから吸い上げるのが、議会機能の大事なところです。私たちの議会では、自治会単位で年40回以上議会報告会を開催しているほか、常任委員会と市内で活動する団体との課題懇談会をやっています。
また、陳情や請願は議会まで来てもらい、直接に意見交換する形にしています。従来は、陳情は年4回の定例会で扱っていましたが、最近は改善し、月に1回のペースとしました。陳情が出されたらすぐに常任委員会で検討できるような形に持っていこうということも取り組んでいます。
こういった取組みと関連し、陳情取扱規程を作成しましたが、たたき台は議員が作りました。それを事務局と市の法制担当とで調整して仕上げてもらいました。現在事務局には残念ながら法制担当がいないため、今回はこのような形をとりましたが、議会事務局改革として法務、法制担当の強化が今後必要になってくると思っています。