2025.02.25 仕事術
第29回 どうする自治基本条例②
自治基本条例制定の意義
所沢市自治基本条例制定の意義としては、常設型の住民投票の規定が設けられたこと、市民参加条例の制定につながったことなどが挙げられます。実際にこの条項に基づき、住民投票が実施されることとなります。また、様々な用語を改めて定義したことも重要でした。
当然ながら、自治基本条例制定に関わった市民の皆さんや、議会において特別委員会に関わった議員を中心に改めて自治とは何かについて学び考える機会を得たことは、所沢市の自治の底上げには有用であったと思われます。最高規範に位置付けなかったことでのデメリットというものは、制定から10年以上を経ましたが特に感じられません。重要なのは条例を制定することではなく、制定された条例が有効に機能しているかということにあります。
住民投票条項を除いて、その点では制定当初の熱意に比べて有効に機能しているという印象はありません。かつて市町村では、市民憲章制定がブームとなった時期がありました。その際も、制定に当たっては相当の熱意が傾けられていたようです。一方で現在、市民憲章は、古い公共施設の銘板となって朽ち果てている事例も散見されます。もちろん市民憲章には、何ら法的な権限はありませんが、自治基本条例は一定の法的な権限を有しています。残念なことに、外国籍住民の住民投票への参加の部分がクローズアップされ、ある種の政治キャンペーンの対象となってしまったことで制定機運がしぼんでしまいましたが、本来的には標準装備となるべき条例だと私は考えています。
議会発議による自治基本条例制定というのはハードルが高いと思いますが、少なくとも執行部から提案された際には、じっくりと審議されることをお勧めします。
また、所沢市自治基本条例の制定過程については、所沢市自治基本条例を育てる会編『市民が取り組んだ条例づくり:市長・職員・市議会とともにつくった所沢市自治基本条例(地方自治ジャーナルブックレットNo.60)』(公人の友社、2013年)が出版されています。この本は、市民側から見た条例制定プロセスが、市議会への不満も含めて詳細に記述されています。こちらも参考にされるとよいかと思われます。ちなみに私も、自治基本条例特別委員長として寄稿させていただいています。
◆書籍情報
『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識―予算・決算・監査を政策サイクルでとらえて財政にコミットできる議員になる―』(2021/3/11発売開始)
江藤俊昭 新川達郎 編著(定価3,300円 (本体:3,000円))
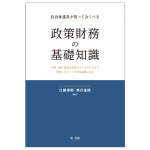
自治体議員が地方財政に主体的に関与・改善したいと考えたときに、本書を読むことで、政策財務の考え方、特に予算・決算・監査に関する基礎的知識や方法論を紹介。先進的な議会の予算決算に関する取り組みや予算案修正の際の考え方や手続き、具体的な修正の手法を知ることができる。








