2024.07.25 仕事術
第23回 どうする議会基本条例③
初めての試みが相次いだ市民意見の聴取
2008年12月の定例会で議会原案がまとまって以後は、原案について市民から意見を聞き、条文に反映させることとなっていました。そのために実施したのが「意見提案(パブリック・コメント)手続」、「公聴会」、「ミニシンポジウム」です。
「意見提案(パブリック・コメント)手続」については、執行部側ではすでに多くの事例を積み重ねていましたが、議会では初めての取組みでした。議会基本条例の条文にも意見提案手続の条項が用意されているのですが、制定前であったため、特別委員会が直接実施することはできず、名目上は議長決裁で議長が主催して実施するという形をとりました。
同様に、ミニシンポジウムについても、議会基本条例施行後は借りた会場がほぼ満席となる市民の方に参加いただきました。議会報告会の一つとして実施できるのですが、制定前のため議長主催となりました。ミニシンポジウムの開催は、議会報告会の実施実績として扱うことができました。また、以後実施することになる議会報告会の開催に大いに役立つことになりました。
公聴会については会議規則にその定めがあったため、特別委員会主催で実施可能でした。公聴人の募集については議会のホームページ、広報を中心に行いました。参加者は7人。公聴人、公述人の公募も所沢市議会初の試みとなりました。こういった取組みの一つひとつが、所沢市議会にとってはほぼ初めてのことでしたので、議会事務局にも大変な負担をかけました。しかし、いったん回路ができてしまうと、以降は、公聴会の開催ハードルが低くなります。
このようにして、議会基本条例を制定しながら、議会の改革を同時並行で進めてきました。
パブリック・コメントは、ありがたいことに11人から76件の意見が寄せられました。回答は、特別委員会の委員が分担して作成しました。普段は、執行部のパブリック・コメントの回答に紋切り型でそっけないと文句をいうばかりでしたが、実際に自分たちで作成してみると、意見を寄せていただいた市民には申し訳なかったのですが、紋切り型の回答が続出してしまいました。パブリック・コメント制度運用は、次回以降に報告予定の自治基本条例制定に関する特別委員会におけるパブリック・コメント手続の対応の基礎となりました。
なぜ、これほど市民意見聴取に時間と手間を割いたかといえば、やはり執行部の新規条例制定以上に、市民の意見を聴取して条例づくりに反映させたいと考えたからです。それによって、この条例の正統性を確かなものとしたいという意味もありました。実際には、「意見提案(パブリック・コメント)手続」、「公聴会」、「ミニシンポジウム」などの市民からの意見聴取によって条例原案が根底から覆されるということはありませんでした。しかし、手続として、しっかり市民意見を聴取することは、「手続的公正」の観点からも重要です。いくら先進的な内容の議会基本条例であったとしても、主権者の市民の声をほとんど聞かずに制定してしまっては、仏つくって魂入れずになってしまいます。
所沢市議会基本条例の独自性
全ての条文について逐条的に説明したいのですが、紙数に限りがあるので、ここでは特に、所沢市議会基本条例独自の条文を中心に紹介します。
(1)閉会中の文書質問
閉会中の文書質問については、執行部側から配慮してもらいたいという要求が出た項目です。当初案では「議員は質問できる」となっていましたが、「議会は質問できる」に修正しました。その後、閉会中の文書質問は、議会運営委員会で常任委員会での全会一致があれば可能であるとしました。さっそく6月定例会閉会後の建設水道常任委員会で文書による質問が行われました。
また、条例制定後の2011年3月定例会が、東日本大震災によって会期途中で中止となったことで、一般質問ができない議員が生じる状況が発生しました。特に、議員活動を引退する議員にとっては最後の一般質問であったため、この閉会中の文書質問の制度を活用して、一般質問を文書質問に代替し、執行部に対して質問しました。これなどは、条文制定時には予期しなかったことであり、皮肉なことに、議会基本条例制定にそれほど前向きでなかった引退する議員のお役に立てました。
(2)附属機関
附属機関については、最も強く執行部側から配慮してもらいたいという要求が出た項目です。多治見市が議会による附属機関の設置を特区申請した際に、総務省から特区として認められませんでした。にもかかわらず、三重県では議会基本条例に附属機関設置条項を盛り込みました。また、所沢市議会の政治倫理規程でも、議長が設置する議員政治倫理審査会の条項をすでに2004年に制定しており、これは事実上の議会の附属機関とみなすこともできます。
また、地方自治法100条の2には「普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる」とあります。この条文は、たとえ学識経験を有する者が単独であったとしても、一種の附属機関であり、事実上、附属機関を容認していると解釈できることなどから、議会基本条例に附属機関条項を盛り込むこととしました。盛り込むに当たっては、法律に書いていないこと(議会の附属機関設置)ができないのではなく、つくるなと書いていないことはできる、という考え方に基づいたことは先ほど述べたとおりです。附属機関の設置については、制定後の議会運営委員会での議論により、全会一致で設置することができることとしました。
制定が可能となった条件
議会基本条例の制定が可能になった条件としては、3点挙げられます。
1点目は積極的な住民参加です。市民の積極的な参加、廣瀬教授をはじめ学識経験者のアドバイスによって、議員内部の議論だけでは、どちらかといえば後ろ向きになってしまう議論を前向きにすることができました。パブリック・コメントや公聴会、ミニシンポジウムへの意見や参加者が少なければ、執行部からも議会基本条例制定に後ろ向きの議員からも、市民の立法ニーズはないのではないかという議論に根拠を与えてしまいます。その点いずれも多くの市民の参加があったことで救われました。
2点目は、特別委員会の名称を議会改革特別委員会とせず、具体的に議会基本条例「制定」特別委員会としたことです。
工程表に合意してもらいながら進めていった点も、制定がかなった大きな要因の一つであるといえるでしょう。
議会基本条例制定を考えた一つの契機は、一般質問の一問一答方式の導入がうまく進まなかったことにあります。どうしても一問一答方式だけを議論してしまうと、そのデメリットに焦点が当たって、なかなか議論が前進しませんでした。一方で、一問一答方式も含む包括的な議会改革案としての議会基本条例であれば、ある意味、一問一答方式が悪目立ちすることがありません。もくろみどおり、それまでの議論が何だったかというぐらい一問一答方式については、条例の制定過程でも争点になりませんでした。
3点目は、特別委員会に属した議員をはじめ、全ての議員の何としてもこの条例を制定するという「熱意」があったことです。これがやはり重要です。この「熱意」ばかりは、ノウハウで何とかできるものではありません。
まだ議会基本条例を制定されていない自治体の議員読者の皆様には、今回の記事を参考にしていただいて、制定をご検討ください。皆さんの議会の事情が許されないのであれば、既存事例のコピーアンドペーストでよいので、自身の理想とする議会基本条例案を案出するという方法も試してみてください。何かと議会活動の発見があるはずです。また、現状において議会基本条例を制定済みの議会におかれては、今回の記事と見比べていただいて、自身の議会基本条例の改定にもお役立てください。
(1) 「所沢市議会基本条例の趣旨及び解釈(令和4年3月29日改正対応版)」(https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shigikai/gikaikaikaku/gikaikihonjyourei/gikaikihonjourei.files/R4.3tikuzyou.pdf)。
************************************
◆書籍情報
『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識―予算・決算・監査を政策サイクルでとらえて財政にコミットできる議員になる―』(2021/3/11発売開始)
江藤俊昭 新川達郎 編著(定価3,300円 (本体:3,000円))
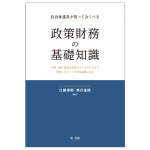
自治体議員が地方財政に主体的に関与・改善したいと考えたときに、本書を読むことで、政策財務の考え方、特に予算・決算・監査に関する基礎的知識や方法論を紹介。先進的な議会の予算決算に関する取り組みや予算案修正の際の考え方や手続き、具体的な修正の手法を知ることができる。








