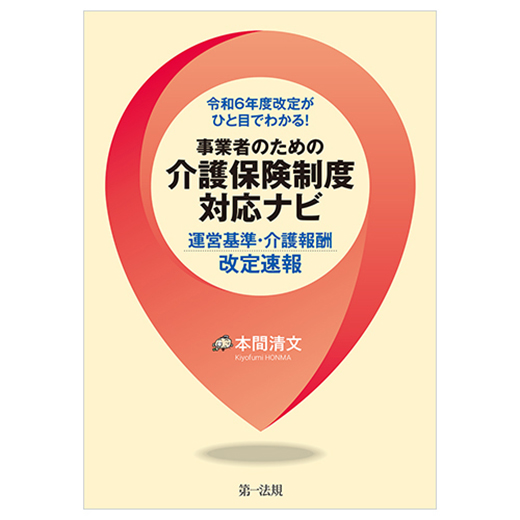2024.05.13 医療・福祉
第4回 地域共生社会の鍵となる金銭管理の支援~日常生活支援事業をめぐって
地域共生社会のために制度充足を
ここまで見てみると、筆者が感じた「相談件数の増加に対して対応するマンパワーが足りていないのでは」という懸念は、都市部において、かなり深刻なのではないかと思います。
そして、この事業の財源に関する問題について、平成30年度日常生活自立支援事業実態調査報告書では「7割以上の社協で事業収支が赤字となっており、運営財源の確保が喫緊の課題」とした上で、「市町村等からの財源支援の検討」の必要性を述べています。また、この事業の重要性がまだまだ浸透していないという課題も挙げています。それ以外にも普及のための課題は多くあることでしょう。
しかし、地域共生社会を進める上で、本事業の普及は不可欠です。例えば認知症の人は、あるとき突然、物忘れが始まり金銭管理ができなくなるのではありません。いえ、もちろん、脳血管疾患などにより、突然、そうした状態になる人もいます。しかし、一方で、加齢により徐々に記憶力が衰え、判断力や日常的な金銭管理能力が低下する人も相当数に上ります(その意味で、本事業は成年後見制度の前段のサービスとして機能する場合も少なくありません)。
その彼らがまず必要とするのは、財産の処分などの法的手続ではなく、今日の食事を買ったり、ホームヘルパーの利用料を支払うといった日常的な金銭管理の支援なのです。
にもかかわらず、本事業が受けられないとなると、どうなるでしょうか。もちろん、明日からの食事に困ります。それは、在宅での生活継続が困難であることに直結し、施設入所などを検討しなければならなくなります。たったそれだけのことが、地域における生活が継続できるか否かの岐路になるのです。
本稿では、筆者が高齢者支援の領域を主戦場としているため、その範囲で記載しました。しかし、同様の問題は障害者支援の領域でも横たわっています。
この事業を必要としている人が、少しでもスムーズに利用できるように、制度面、財源面など様々な角度からのテコ入れが必要な時期ではないかと思います。その第一段階として、まずは、本事業に関するニーズなどの詳細な実態調査を国や自治体などで行う必要があるかと思います。
(1) 厚生労働省「福祉サービス利用援助事業について」(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1119-7e.pdf)
(2) 全国社会福祉協議会「日常生活自立支援事業の今後の展開に向けて~地域での暮らしを支える意思決定支援と権利擁護(平成30年度日常生活自立支援事業実態調査報告書)」(2018年)(https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/research/20190419_nichiji.html)
〔追記〕 このたび、当サイト運営法人である第一法規より、下記を出版させていただきました。介護保険に関わる方々の一助となれば幸いです。
●令和6年度改定がひと目でわかる! 事業者のための介護保険制度対応ナビ ─運営基準・介護報酬改定速報─
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104854.html