2024.04.10 仕事術
第18回 どうする常任委員会①
議会基本条例で常任委員会の役割を明確化
2009年3月に制定された所沢市議会基本条例18条で、「委員会の委員長及び副委員長は、市民の要請に応えるため、所管委員会に係る市政の課題に対し、常に問題意識を持って委員会を運営するとともに、政策立案及び政策提言を積極的に行うよう努めなければならない」と定めました。
この条文にあるように、委員会で政策提言を行い、その政策提言が市の施策に実際に反映されたケースについて紹介します。所沢市議会基本条例制定後の2010年3月定例会で、教育福祉常任委員会が「療育支援センター」についての政策提言を行いました。私としては、議会基本条例制定時の委員長として、この18条を実際に形にしたいという思いと、療育支援は私の議員としての重要なテーマであったこともありました。
当時の委員長は幼稚園教諭の経験がある方で、この政策提言の提案にも賛同いただきました。他の委員の方も賛同してくださいました。
最終的には、2010年3月議会において、委員長報告の形式で提言案を報告しました。委員会からの政策提言というのをどう取り扱うのかについても議論がありましたが、委員長報告とすることをもって提言としようということになりました。
少し長いですが、政策提言としてどの程度の精度で記述しているかも含めて理解していただきたいので、全文を引用します。
教育福祉常任委員会
1.療育センターの3つの機能。
療育センターとして以下の3つの機能を有することを要望する。
① 通園機能。
地域の保育園に通っている子どもが利用できるように、並行通園(小学校でいう通級)ができるようにすること。高機能自閉症、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥・多動性障害)の子どもに直接支援を行える場を再整備すること。
② 診療・療育機能。
将来的には、医師による診療・投薬等や、臨床心理士、ST(言語聴覚士)、OT(作業療法士)、PT(理学療法士)など専門家による個別・集団訓練を行うこと。
③ 相談機能(発達相談(来所)、巡回相談)。
早期発見を早期療育につなげるための保護者への支援を行うこと。保護者の障害受容により早期療育が可能となる。保護者の障害受容を促すため、個別相談だけでなくさまざまな支援メニューを用意して実施すること。例えば、ペアレントトレーニング、ピアサポート(親の会の相談会)、レスパイト(ショートステイ)、家庭訪問による相談などである。さらに、子どもの評価を行い、保育園等に子どもの支援方法についても助言を行うこと。
2.支援対象者の個別データの一括管理と活用。
出生時から就労・自立までの個別データ・カルテ(心理検査結果、過去の支援情報、アセスメント、対応履歴、診断、所見など)をセンター及び保護者が共有するとともに、保育園、幼稚園、市や県の教育委員会(就学支援委員会、生涯学習推進センターの教育臨床エリア)、就労支援センターなど関係機関にも情報を提供すること。なお、関係機関への情報提供に当たっては、保護者に承認を得ること。
3.既存施設やサービスの有効活用と有機的連携。
愛知県豊田市のような各機能と提供場所が一体化した施設が理想的であるが、場所を決めようとすると時間がかかり、今ここにある問題への対応が遅れるので、センターそのものが具体的な療育を行う場所となることには必ずしもこだわらない。コーディネーターを置き、医療療育や就学、高等教育との連携を行うこと。ハコモノではなく、コーディネーターなどの人に重点的に投資すること。現状においても、各機関がそれぞれ出来ることを精一杯取り組んではいるが、地域の機関全体で役割分担をすること。そして、療育センターがそれらを取りまとめること。
4.個別ケア会議、地域支援ネットワーク会議の定期開催。
療育支援センターが地域のコーディネーターの役となり、支援対象者に対する個別ケア及び地域支援ネットワーク会議を取りまとめること。
内容を見ていただければ分かるとおり、この提言はいわゆる施設のハコモノ整備に関する提案ではなく、療育支援センターの中身はどうあるべきか、という観点からまとめました。
この提言の素案は、療育を必要とされる保護者の要望や私のそれまでの一般質問、委員会でのこのテーマに関する質疑応答も踏まえて作成し、委員会委員の皆さんから意見をいただきながら成案にまとめました。
その後、所沢市では、こども支援センターの計画に、この提案を盛り込んだ機能を整備することとなりました。所沢市が2016年3月に発行した「所沢市こども支援センター運営方針」の「こども支援センターに関する検討経過」にも、次のようにこの議会の提言が記述されています。
市議会教育福祉常任委員会が、市が整備すべき療育支援センターについて、次の4点を提言しました。
1 療育センターの3つの機能(通園、診療・療育、相談)
2 支援対象者の個別データの一括管理と活用
3 既存施設やサービスの有効活用と有機的連携
4 個別ケア会議、地域支援ネットワーク会議の定期開催
これを受けてというだけではないと思いますが、結果的に「所沢市こども支援センター」には「療育支援機能」を整えていただくことができました。提言が政策決定過程で一定の扱いを受けることができたのは、議会の思いつきではなく、療育支援に関心のある職員の方々の組織の中では諸事情があり、発言できない思いもくみ取っていたことが要因の一つであったと私は考えています。
この提言をきっかけに、その後も常任委員会から提言を行うことが当たり前になっていきました。直近でも2023年3月定例会で、特別委員会からまちづくりの提言、2022年には「地域福祉」についての提言などが行われました。
ぜひとも、皆さんの議会の常任委員会も、単なる議案や請願等の審査にとどまることなく「所管事務調査権」を積極的に行使して、住民の役に立てる議会を目指してください。
次回は請願等の審査について考えてみましょう。
************************************
◆書籍情報
『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識―予算・決算・監査を政策サイクルでとらえて財政にコミットできる議員になる―』(2021/3/11発売開始)
江藤俊昭 新川達郎 編著(定価3,300円 (本体:3,000円))
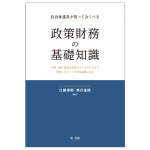
自治体議員が地方財政に主体的に関与・改善したいと考えたときに、本書を読むことで、政策財務の考え方、特に予算・決算・監査に関する基礎的知識や方法論を紹介。先進的な議会の予算決算に関する取り組みや予算案修正の際の考え方や手続き、具体的な修正の手法を知ることができる。








