2024.02.13 仕事術
第15回 どうする予算①
ある老朽化施設についての質問が、施設の新築移転に発展
そして、できれば議会と執行部の合意の下、予算調整権を有する執行部から新規予算が提案されることが理想的です。かつて、ある学齢期前の障害者施設の老朽化問題を平成20年6月の一般質問で取り上げたことがあります。仲のよかった信頼する市職員がたまたまその施設に異動となった(うわさでは、ある案件で上司の不興を買ったために左遷されて、その施設に飛ばされた)ため、市内でもはずれにあるその施設を初めて訪問しました。
そして、ビックリしました。施設が老朽化していたこともさることながら、職員のトイレが男女一緒だったのです。おそらくその時点では、市の施設でトイレが男女一緒というのは、その施設だけだったのではないでしょうか。そこで、一般質問で、この施設について質問することにしました。調べていくうちに、「移転または建て替えを願いたき件について」ということで、平成8年の6月議会で採択されていることが分かりました。「移転又は建て替えをするべきでは」との私からの質問に対して、市長からは「建て替えを考えているところ」という答弁があり、腰が抜けるほどビックリしたことがあります。
当時の市長は、先述した市長等の報酬引き下げを提案し、私が予算修正案を提案して、引き下げを修正した市長でした。いわば市長から見て、私は敵対する立場だったのです。その私の質問に対して前向きな答弁をした市長も、今から考えると懐の深い方でした。その後、平成24年にはより市の中心部への新築移転がなされました。おそらくは、先ほども説明したように、私が質問した時期と、執行部が施設の移転を検討していた時期が一緒だったにすぎないかもしれませんが、ある職員からの伝聞では、私の質問に対する答弁調整において、市長が「建て替えの検討をすることとなった」と発言したという話もありました。真相は闇の中ですが、そもそも市議会において移転ないし建て替えの請願が採択されていたことを背景に、私の質問がきっかけとなって、市中心部への新築移転が実現したと、外形的にはいえなくもありません。
一方で、一般質問などを経ずに予算化した事例もあります。私の住まいの学区の中学校に、私が懇意にしている方の娘さんが進学することになりました。その娘さんは、車椅子で小学校に登校していました。その小学校は、建て替えたばかりであったため、給食を運搬するための人貨両用のエレベーターが設置されていました。そのため、そのエレベーターを使って上の階へ移動して事なきを得ていました。ところが、中学校には、そういったエレベーターがありませんでした。お母様からも何とかしてほしいという要望があり、エレベーターはさすがに無理だと思ったので、費用的には安価な階段昇降機を設置できないかと教育委員会の教育総務課に相談を持ちかけましたが、なかなか色よい返事はもらえませんでした。進学予定の中学校にも出向いて対応策への協力をお願いしましたが、当時の校長からは、「生徒がみんなでその子と車椅子を抱えて階段を昇降するのも教育です」と、とんちんかんな答えが返ってきました。車椅子の移動にも支障のない施設の整った学校に行くのがよいのではないかと示唆されることもありました。隣の市では、同じような事例に直面した親が、学校に多額の寄附(数百万単位)をしてエレベーターを設置したという話もありました。残念ながら、私が相談を受けた方にはそれほどの財力はありません。いよいよ諦めかけていたとき、当時の教育総務部長が「議員さん、エレベーターつけましょうよ」というのです。このときも本当にビックリしました。遠因には、親が多額の寄附をした隣の市の事例に対し批判が集まっていたこともあったようです。親にそこまで求めるのかという議論もあったためです。
エレベーター設置に当たっての工事費を改めて確認したところ3,700万円でした(所沢市議会平成17年9月定例会議事録)。
また、近隣の公民館の建て替えに当たって、新たに図書館も含めた複合施設を建設する計画が持ち上がりました。この頃は、新たな施設建設の際には、住民を巻き込んだワークショップを開催することがはやりでした。私は、老朽化した近くの児童館も移転し、この複合施設の計画に含めたいと思っていました。そこで、児童館に子どもを通わせていた保護者数人と相談し、ワークショップに参加しました。ワークショップでは、「新しい複合施設には、児童館を含めるべきだ」という意見を強く主張してもらいました。結果的には、当初予定になかった児童館が新しい複合施設に新設されることになりました。これにも「まさかこんなにうまくいくとは」と、驚きました。
私が体験したささやかな事例ですが、必要性のある事業については、議員が住民とともに、その必要性を議場で、あるいは非公式な働きかけを通じて、しっかりと執行部に訴えることで、時には予算化されることもあるということです。
なるべく、そうした手順を踏んだ上で、それでも執行部が動かないようであれば、あるいは、場合によっては先ほど紹介した市内小中学校へのエアコン設置計画を当時の市長が白紙に戻したケースのように住民投票を実施するという方法をとらざるを得ないこともあります。この事案では、結果的に、住民投票で設置を求める声が大きかったことから、当時の市長はエアコン設置をいやいやながら決断しました。
そのときはそういった思いに至りませんでしたが、小中学校のエアコン設置問題について、あるいは識者が指摘したように、より小規模な財源確保ができる範囲での増額修正提案という方法もあったのかもしれません。もっともその当時は、その増額修正案をまとめ上げ、賛成多数に持ち込むまでの力量もありませんでしたが。
以上挙げた私の事例は、議員単独での活動による予算化です。しかし、本来であれば、個人の政策を、議会としての政策要望に昇華させて予算化を実現するのが王道です。この話はまた別の機会に。
次回以降は、予算化するのではなく、いかに予算の無駄をチェックするかについて検討します。
(1) 「審議」と「審査」の違いについては、福岡市議会「議会用語集」(https://gikai.city.fukuoka.lg.jp/yougoshu)を参照。
(2) 野村憲一「職員なら押さえたい! 議会ってトコロの勘どころ 第5回 予算の修正案」(議員NAVI 2019年11月11日号(https://gnv-jg.d1-law.com/login/article/20191111/18038/2/)。
(3) 佐々木まこと「少人数学級に関する増額修正可決成立!」(2010年3月24日)(https://sasakimakoto.net/blog/entry-4209.html)。
(4) 木田弥「予算修正のすゝめ 第1回 予算修正は議会改革の一里塚」(議員NAVI 2018年2月26日号)(https://gnv-jg.d1-law.com/login/article/20180226/10762/)。
(5) 「尾木ママ 所沢の住民投票で議会批判」(デイリー2015年2月17日)(https://www.daily.co.jp/newsflash/gossip/2015/02/17/0007746649.shtml#google_vignette)。
************************************
◆書籍情報
『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識―予算・決算・監査を政策サイクルでとらえて財政にコミットできる議員になる―』(2021/3/11発売開始)
江藤俊昭 新川達郎 編著(定価3,300円 (本体:3,000円))
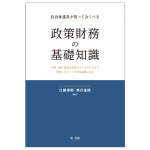
自治体議員が地方財政に主体的に関与・改善したいと考えたときに、本書を読むことで、政策財務の考え方、特に予算・決算・監査に関する基礎的知識や方法論を紹介。先進的な議会の予算決算に関する取り組みや予算案修正の際の考え方や手続き、具体的な修正の手法を知ることができる。








