2024.01.12 仕事術
第14回 どうする定数③
定数を考えることは議会制民主主義を考えること
以上が、所沢市議会の定数改正をめぐる議論の概要でした。住民にとって議員はコストと考えるのか、それとも権利と考えるのか、その違いが明確に現れた議論でした。私は、権利と考える立場に立っています。ただ、定数については、減らすことは不可避と考えていました。実際の住民の投票行動においては、コストと捉え、定数や報酬削減を公約として訴える候補者に票が集まります。その溝は埋まることなく議論は進みました。現実的な成果は、少なくとも所沢市議会は自らの定数を自らで定義したことです。常任委員会の数は4が望ましく、各委員会は最低8人必要という定義です。また、議会基本条例で定めた定数や報酬の改正議案提出に当たっては、「明確な改正理由を付す」という条文にのっとって決定された点も大きな成果です。
一方で、もう少し議会の存在意義についてより深い議論があってもよかったと思います。私は、議会や議員は消防や警察と同じ側面を有していると考えています。住民の権利が行政によって侵害されるような政策が実施される場合、制度として異議申立てができるのが議会です。消防や警察が火事や泥棒が減ったから定数を減らそうという議論はあまり想定できないのと同様に、議会は存在そのものが重要ですし、もし何らかの異議申立てをするに当たって行政組織に対抗するためには、一定数の議員は必要です。そういったそもそも議会とは、という議論はあまりできませんでした。もっとも、C委員は聞く耳を持たなかったでしょうが。
昨春の統一地方選挙でも、定数削減を訴えた新人議員の方々が多く当選しました。定数削減の検討に当たっては、所沢市議会の事例を新人議員の方々にも参考にしていただくことを願っています。
(1) https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shigikai/aramashi/teisuu/sgikai_20121017180713985.html
************************************
◆書籍情報
『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識―予算・決算・監査を政策サイクルでとらえて財政にコミットできる議員になる―』(2021/3/11発売開始)
江藤俊昭 新川達郎 編著(定価3,300円 (本体:3,000円))
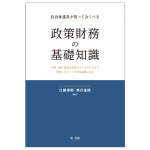
自治体議員が地方財政に主体的に関与・改善したいと考えたときに、本書を読むことで、政策財務の考え方、特に予算・決算・監査に関する基礎的知識や方法論を紹介。先進的な議会の予算決算に関する取り組みや予算案修正の際の考え方や手続き、具体的な修正の手法を知ることができる。








