2023.12.25 仕事術
第13回 どうする定数②
市議会議員の見解もアンケートやヒアリングなどを実施して聴取
こうした審議会の通例として、まずは、議員定数の議論を行うための審議会など何らかの会議体を設置した事例を参照します。そのために参考としたのが、会津若松市の「『議会活動と議員定数等との関連性及びそれらのあり方』最終報告(案)」、北海道福島町議会基本条例諮問会議「議員定数と議員歳費に関する答申」、生駒市行政改革推進委員会行政委員会報酬等検討部会「議員及び特別職報酬等の適正化に向けた提言」です。
いずれの報告や答申、提言も大変参考になったことはいうまでもありません。ただ、上記の事例はいずれも報酬と定数を同時に検討しており、所沢市議会の場合は、連載第11回「どうする議員報酬」でも少し触れたように、基本的には定数単独で議論することとしたため、これら三つの事例とは趣を異にしていました。
これらの先行事例検討等から、定数を議論する上で必要となるデータとして、当初資料にあった「所沢市議会の現状」、「議員定数の推移」、「所沢市の財政状況」、「中核市・特例市の状況」に加え、現在人口と「上限定数」との相関関係、埼玉県内39市の議員定数等について、所沢市の歳出予算の推移、一般会計予算額、議会費及び議員数等の推移、議会基本条例制定後の活動状況、議会活動比較表(平成23年度と平成20年度の比較)などを追加資料として、新たに提供することとしました。
ちなみに、生駒市の事例は、首長の諮問機関として設置された生駒市行政改革推進委員会の内部に設置された行政委員会報酬等検討部会による提言となっています。また、福島町の場合は、福島町議会の附属機関である福島町議会基本条例諮問会議からの答申という形式をとっています。会津若松市議会の場合は、特別委員会の議会制度検討委員会が作成した案について、政策討論会や市民との意見交換会で議会内及び会津若松市民と意見交換を進めながら最終報告をとりまとめています。会議体の設置主体や取組方法も三者三様といえます。旭川市議会では、議会設置の定数を検討する会議体の事例として会津若松市、福島町、そして所沢市の三つの事例を比較した表を作成されています(https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/council/6600/6630/p001632_d/fil/siryo01.pdf)。
その後、所沢市議会のように「あり方審議会」を設置して検討した事例として、米原市議会、気仙沼市議会などが確認できました。
先進事例の資料に加え、所沢市議会議員の見解を確認するために、直近の平成23年4月の選挙公報も資料として「あり方審議会」に提供されました。さらに、議員へのアンケート調査、各常任委員会の委員長と副委員長10人を対象にしたヒアリング調査を「あり方審議会」に実施してもらいました。
「あり方審議会」による答申の記載によれば、平成23年4月の所沢市議会議員選挙公報の調査結果では、立候補46人中14人の候補者が議員定数の削減を公約に掲げ、うち1人が市民参加による見直しを公約に掲げていました。私は、その14人には入っていませんが、結果的には、この定数見直しの一連の議論に大きく巻き込まれることになってしまいました。さらには、1人を除いて具体的な人数を示さない形での公約でした。1人は24人への削減を公約として訴えていました。増員を公約した候補者はいませんでした。また、選挙で削減を公約した候補者の総得票数(落選も含む)は4万394票(有効投票総数の36.2%)でした。この数字をどう分析するかですが、やはり定数削減については有権者に一定の支持があると見るのか、あるいは、そうでないと見るのか。答申では「市民の中でも拮抗している状況にあると見ることができる」とまとめています。
削減を求める議員の多くは定数36人に対して33〜34人を主張
市議会議員へのアンケート調査の結果も紹介します。当時の36人の議員全員が回答しました。結果としては、現状より増やすべきと回答した議員が6人、減らすべきとした議員が18人、減らすべきと回答した議員のうち1人が定数24人を主張、13人が定数33人から34人と回答し、うち8人が定数33人と回答しました。このアンケート結果から直接決まったわけではありませんが、結果的に現在の所沢市議会の定数は33人になっています。なお、答申から条例改正までの経緯については改めて詳述します。
アンケートの自由記述欄には削減の理由として市の財政状況に言及する者が多く、また、前期の議会で欠員が生じていて33人で議会運営をしたが、特に支障がなかったという見解もありました。一方で、やはり欠員状態はよくなかったとの意見もありました。
各常任委員会の委員長と副委員長10人を対象にしたヒアリング調査では、こうしたアンケート調査結果も参考にしながら率直な意見交換をしていただきました。
まず確認したのが、常任委員会の設置数です。所沢市議会は、本会議主義ではなく委員会主義の議会ですから、議案の実質的な審議は委員会が中心になります。この点については、全員が現状の4が望ましいという意見で一致しました。
続いて、委員会の構成員数は何人がよいかという点についても意見を交換しました。その結果、当時の9人と8人では実質的な違いはないのではないかという意見と、やはり9人の方が意見の多様性や議論の活発さを維持するのに必要という意見に分かれました。
さらに、前期が途中から33人で議会が運営されていたことについての評価においても、問題はなかったという意見と、やはり多様性が損なわれたという意見に分かれました。一方で、各常任委員会の委員数を7人以下にした方がよいという意見はなかったようです。
また、全体として、所沢市は行政区が11、小学校区が32、中学校区が15である現状からも、定数30人程度は必要という意見や、人口1万人当たり1人程度がよいのではないかという意見も出されました(所沢市の人口は約34万人)。
こうした様々な検討を経つつも、一方では、実際の「あり方審議会」は様々な事情も重なって迷走し、一時は答申の作成が無理なのではないか、というところまで追い込まれていきます。
その詳細は、次回お伝えします。
◆書籍情報
『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識―予算・決算・監査を政策サイクルでとらえて財政にコミットできる議員になる―』(2021/3/11発売開始)
江藤俊昭 新川達郎 編著(定価3,300円 (本体:3,000円))
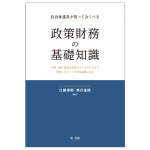
自治体議員が地方財政に主体的に関与・改善したいと考えたときに、本書を読むことで、政策財務の考え方、特に予算・決算・監査に関する基礎的知識や方法論を紹介。先進的な議会の予算決算に関する取り組みや予算案修正の際の考え方や手続き、具体的な修正の手法を知ることができる。








