2023.12.11 仕事術
第12回 どうする定数①
所沢市議会の定数も揺れ動いてきた
議員定数を考える上で、法定数若しくは法定上限数が定められていた時代にも所沢市議会では様々な動きがありました。
所沢市の場合、市政施行が昭和25年。この時点で、議員定数は法定で30人。その後、人口増加に伴い、36人、44人と増えてきました。しかし、昭和57年第3回定例会において「所沢市議会議員の定数を減少する条例について」という請願が賛成多数で採択されます。当時の事情を知る先輩議員によると、市内自治会連合会の人たちが中心となって請願活動が行われたようです。実際に同様の活動を実施した他市の事例に触発されたともいわれています。自治会は、今はそれほどではありませんが、当時は集票活動に一定の影響力を有していたために、議員も賛同せざるを得なかったようです。
自治会関係の人たちは、「自分たちはほぼボランティアで自治会活動をしているのに、議員は大した仕事もしていないように見えるのに、高い給料をもらっている」ことについてのわだかまりが根底にあるようです。
昨年も同様に、自治会連合会関係者が中心となった「通年議会に反対する活動」が、「通年議会が制度化されると執行部は議会対応で さらに忙しくなる」という間違った情報に基づき、活発に繰り広げられました。所沢市においては、自治会連合会と地方議員の間には、根底に緊張関係があるようです。さらには、自治会の重鎮の機嫌を損ねたくない議員の一部、通年議会の制度化により議会の権限が強化されることに忌避感を持つ執行部の一部も蠢(うごめ)いていたようです。
その後もこの勝ちパターンを覚えていた一部住民が同様の請願を出しましたが、特に議会基本条例制定以降は、定数についての根拠のない請願は不採択となりました。
さて、昭和57年には賛成多数で請願が採択されたことから、法定数が44人のところ、40人に減らすことになりました。自治法では、条例制定及び改廃の直接請求権が制度として設けられています。自治法によれば、選挙権を有する者の50分の1以上の連署によることとされています。にもかかわらず、議会の請願審査で安易に実質的な条例改正が実現するのは、少し疑問が残ります。
その後、ここからが時代を先取りしていたといえるのですが、平成2年第3回定例会において、当時の市長から、「所沢市議会の議員の定数を減少する条例の一部を改正する条例について」とする議案が提出されます。議員定数を40人から30人にするという思い切った提案でした。当時の市長は弁護士で、議会とも常に緊張関係にありました。さすがに議会としても、そのまま市長提案に乗るわけにはいかず、賛成少数で否決されましたが、一方で市長提案を全く無視するわけにもいかなかったせいか、18人の議員から同じく、定数を40人から36人に減らす一部改正条例案が提出され可決しました。この時点で、所沢市の人口は30万人を超えており、法定数は48人でしたので、12人減らしていたことになります。
その後、平成11年の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」いわゆる地方分権一括法により、議員定数は法定数から法定上限数へと改正され、上限は46人とされたので、上限から10人減少している状態になりました。この法改正を受け、36人の定数を改めて定めるために「所沢市議会議員定数条例の制定について」の議案が可決します。本来であれば、この法定上限数に変わった時点で、ゼロベースで議員定数を見直すべきだったともいえます。
その後、平成23年の法改正により、法定上限数が撤廃されました。所沢市議会としても、平成21年の議会基本条例の制定により、議員報酬や定数の見直しに当たってのルールを定めていたこと、同様に、附属機関設置のルールも定めていたことなど、定数を本格的に見直す環境も整ったため、改選間近での票目当ての議論ではなく、改選後1年目の平成23年から、次期改選に向けての見直しに取り組むことになりました。その詳細については次回ご報告します。
■参考資料
◇所沢市議会議員定数のあり方に関する審議会「議員定数の算出根拠について(答申)」(平成24年11月)(https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shigikai/aramashi/teisuu/sgikai_20121017180713985.html)
◆書籍情報
『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識―予算・決算・監査を政策サイクルでとらえて財政にコミットできる議員になる―』(2021/3/11発売開始)
江藤俊昭 新川達郎 編著(定価3,300円 (本体:3,000円))
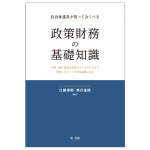
自治体議員が地方財政に主体的に関与・改善したいと考えたときに、本書を読むことで、政策財務の考え方、特に予算・決算・監査に関する基礎的知識や方法論を紹介。先進的な議会の予算決算に関する取り組みや予算案修正の際の考え方や手続き、具体的な修正の手法を知ることができる。








