2023.10.25 仕事術
第10回 どうする政策条例
議員提案条例制定に至る我が市議会の経験
さて、埼玉県議会は活発に議員提案条例を制定していますが、遡ることおおよそ25年前の1997年3月に、所沢市議会では、ダイオキシン問題への住民からの切なる要望に対応するため、「ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すための条例」(以下「ダイオキシン条例」といいます)を制定しています。これは、埼玉県内のみならず、全国的にもほぼ初めての、地方議会発の議員提案政策条例といわれています。
私は当時、まだ市議会議員ではありませんでしたが、市議会議員になり立ての頃には、ダイオキシン条例制定に関わった議員も多く、様々な武勇伝を先輩議員から聞くことができました。
この条例制定の記録を残そうと思い、私が議長のときに、所沢市議会65周年記念誌を作成しました。この記念誌の特集テーマが、「いま、改めて振り返る『ダイオキシンを少なくし所沢にきれいな空気を取り戻すための条例』制定について」でした。
この特集から、議員提案条例制定の経過を改めて確認したいと思います。
ダイオキシン条例に罰則や規制値を盛り込むことは断念
所沢市のくぬぎ山といわれる地域とその周辺には、廃棄物処理のための小型焼却炉が林立していました。ただ、設備が小規模であったため、燃焼温度も低く、そのため猛毒といわれるダイオキシン類の発生が懸念される状況でした。周辺住民の心配も募り、1995年には住民の独自調査が行われました。その結果、ダイオキシンが検出され、同年12月の市議会ではこの問題についての一般質問が行われました。しかし、執行部側もまだ十分な知見がなく、納得いく答弁は得られませんでした。
議会は、1996年6月に、住民の要望を受ける形で「環境対策特別委員会」を設置。同年11月には、法的措置を伴うダイオキシン条例の作成を行う方針を決定しました。
執行部には当時、そして現在もですが、県議会ほどには条例を制定するためのスタッフ体制は整っておらず、議員自らが会議室に集まって、ホワイトボードに書き込みながら夜中まで条文案を検討したそうです。
執行部側、そして議会事務局からの協力も十分に得られない状況下で、条例として機能しないような、瑕疵(かし)のある条例としないように、公害問題に詳しい弁護士や学識経験者からもアドバイスを受けたそうです。条例制定に当たって、理念的な内容とする案、罰則や規制値も含めた大気汚染防止法の横出し規制を目指す案の主に二つに分かれて検討したそうです。やはり、既存の法律を超えた罰則や規制などを制定しても、実際には検察が起訴しない可能性も高かったことから、最終的には罰則や規制値のない理念的な条例を制定することとしました。特別委員会内部での議論だけでは、委員会以外の議員の納得が得られないということで、全員協議会も開催して、全議員が納得する形に修正なども加えたそうです。そうして、ようやく1997年3月定例会において、全会一致で可決しました。
わずか8条の理念的な条例ですが、条例に反する者への勧告や、勧告に従わない者に対して事業者名等を公表するものとする、という条文も備えています。
また、条例制定以後は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条、15条の規定に基づく県の要領により知事から市に対して照会があった場合、速やかに議会に報告し意見を求めること、という条文も備えています。この条文の実効性を高めるため、執行部側も「所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例」を1999年に制定しました。新しい廃棄物処理施設の建設や既存施設の変更などの情報を県が市に対して提供し、市は議会に報告する方式が整備されました。実質的に許認可権限はないのですが、許認可権限を持つ県に対して意見具申できるという制度の建付けになっています。
そうした実績を有しながらも、我が市議会では、政策型の議員提案条例は、その後、しばらくは提案されないまま時が過ぎてしまいました。やはり、市議会レベルで議員提案条例を制定することは、相当しんどいことだったようです。
17年ぶりに議員提案の政策条例が制定
正確にいえば、2009年に議会基本条例が制定されているのですが、議会基本条例は政策条例ではないので、それを除いて2014年に17年ぶりに制定されたのが、「所沢市歯科口腔保険の推進に関する条例」です。この条例はある議員が通っていた歯科医の働きかけがきっかけとなりました。条例そのものは全国初ということではなく、各地の歯科医師会がそれぞれの地方議会に熱心に働きかけていたそうで、2014年4月1日時点で、全国65市2区13町2村で制定済みとなっていました。
制定に当たっては、議会基本条例にのっとり、教育福祉常任委員会において参考人として所沢市歯科医師会会長を正式に招致して意見を伺い、市の条例担当部局からも1条ごとに対案を提案してもらいました。また、条例案についてのパブリックコメントを議会が実施するなど、制定過程においても瑕疵がないように進めました。できれば、条例案についての公聴会を行えるとよかったのですが、時間の制約もあり断念しました。
議会によっては、実績づくりのために議員提案の政策条例を拙速に制定し、執行部とのすり合わせが不十分であったため機能しない事例や、罰則規定を警察や検察と協議しないまま制定したために、条例違反で警察に告発しても、瑕疵ある条例として検察が起訴を見送った事例などが散見されます。
実際には、予算制定権や自力執行力がない議会が制定する政策条例は、やはり理念条例にとどまってしまうことはやむを得ないところです。
それでもなお、政策条例を制定するプロセスを丁寧に進めることによって、住民意見の集約や、執行部とのすり合わせを通じた意見交換ができるなど、最終的に成案に至らなかったとしても、執行部提案の政策条例について、より深い理解が得られるなどのメリットも期待できます。
ぜひ皆さんも、上記の事例を参考にしながら、住民要望を起点とした政策条例策定を目指して議員活動を進めてみてはいかがでしょうか。
◆書籍情報
『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識―予算・決算・監査を政策サイクルでとらえて財政にコミットできる議員になる―』(2021/3/11発売開始)
江藤俊昭 新川達郎 編著(定価3,300円 (本体:3,000円))
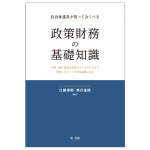
自治体議員が地方財政に主体的に関与・改善したいと考えたときに、本書を読むことで、政策財務の考え方、特に予算・決算・監査に関する基礎的知識や方法論を紹介。先進的な議会の予算決算に関する取り組みや予算案修正の際の考え方や手続き、具体的な修正の手法を知ることができる。








