2023.05.12 仕事術
第1回 どうする会派①
擬似的な会派のおかげでデメリットを感じなくて済んだが
私の場合も当選1年目には、先輩議員や同じく当選した新人議員から会派加入の誘いを受けました。今はない政党会派(D党)からも、「君については会派拘束しない」、つまり会派の意向はともあれ、反対したい場合はしてよい、との条件を示されて誘われたのですが、正式に加入するとも答えていないのに、「彼はうちの会派に入る」と代表者会議で報告されてしまいました。幸い、会派加入の誘いを受けた別の保守系会派の先輩議員が、「そんなはずないだろう」と抗弁してくれたおかげで、勝手に会派に入れられる事態は免れました。そんなこともあり、当面は1人で活動しようと考え、1人会派を選択しました。
初当選時は複雑な事情を抱えた選挙だったので、1人会派が八つもできてしまいました。会派すべてに割り振れるほど会派控え室は用意されていなかったので、私は、別の1人会派の議員2人と部屋を共有することになりました。私以外の2人は、Y氏とO氏。Y氏は、既に市議会議員を3期経験。市長選にも出馬経験あり。O氏は、お父上が県議会議員の重鎮。2人とも、議会や議員の背景、地域の実情によく精通していました。おかげで、1人会派でありながら、擬似的な会派に所属していたごとき1年となりました。
基本的には1人会派のため、代表者会議には出席できません。そのため、会議の内容は、議会事務局職員からの結論の伝達に頼るしかありません。しかし、Y氏が以前同じ会派に属していた先輩議員から、議会事務局職員からは聞き出せないような議論の過程やその裏事情も含めて、結論に至る情報を教えてくれ、さらにその歴史的背景まで含めて解説してくれました。代表者会議の1年後にこの疑似的な会派は解散することになるのですが、D党の会派に所属した新人議員の場合、結論しか聞かされていなかったようで、結論に至る情報については、1人会派ではありましたが、彼らよりはるかに詳しくなりました。
議案レクチャーも3人共同で行いました。この点はまた次回に紹介しますが、これが実に勉強になりました。
政党会派や大会派に所属した場合でも、他会派の議員とは連絡を取り合って、特に、結論に至るプロセスも代表が丁寧に説明する風通しのよい会派の議員からは、代表者会議の様子など、結論に至るプロセスについての「ウラ」をとっておくことを心がけた方がよいでしょう。
この3人で会派を組む話もあったのですが、やはり基本的なところで価値観が合わなかったことから、2年目には、それぞれ別の会派に所属することとなりました。(つづく)
◆書籍情報
『自治体議員が知っておくべき政策財務の基礎知識―予算・決算・監査を政策サイクルでとらえて財政にコミットできる議員になる―』(2021/3/11発売開始)
江藤俊昭 新川達郎 編著(定価3,300円 (本体:3,000円))
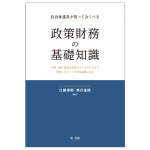
自治体議員が地方財政に主体的に関与・改善したいと考えたときに、本書を読むことで、政策財務の考え方、特に予算・決算・監査に関する基礎的知識や方法論を紹介。先進的な議会の予算決算に関する取り組みや予算案修正の際の考え方や手続き、具体的な修正の手法を知ることができる。








