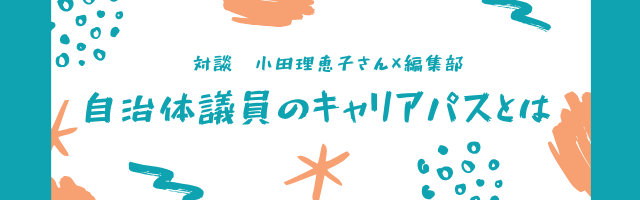編集部 何故この3市を選んだのでしょうか?
小田 官民連携事業を進めていくうえで、これらの自治体に可能性を感じたからです。この3市のエリアは実は池袋から電車で最短18分でアクセスできますし、渋谷からも乗り換えなしで1本で行けるんです。都心から近いというのは、かなり条件がいいと思います。
編集部 当日はどのような進行だったのですか。
小田 市長それぞれにプレゼンテーションをご用意頂いて、そのあとに自治体と企業のマッチング会を開催しました。分かりやすく言えば、一対一のお見合いではなく、合コン形式です。
編集部 参加者はどんな方がいらしたんですか。
小田 参加者は基本的にビジネスパーソンメインでしたが、3市の議員にもお声かけし、来ていただきました。開催の事前にご相談に乗って頂いたりした議員もいます。当日は18名の議員がお越し下さって、興味を持って頂いて嬉しかったです。地元の企業でなく、東京の企業と組むことへの抵抗感がおありかなとも心配していたので。
編集部 官民連携の新しい分野では、地元企業だけで進めるというのも難しいのかもしれませんね。
小田 確かに、東京からお金をもっていくという話なので、地元の企業しか連携しないということになると、非常に連携はしづらいですよね。
ところで、今回の市長ピッチとは直接に関係しませんが、東村山市は「民間事業者提案制度」という非常に面白い取組みをされているんですよ。これは民間事業者の主体的な発意によって市民サービスの質や満足度などを向上させるための事業等の提案を公募で受け付ける仕組みで、協議が整った場合は、提案者を実施者として事業化するもの、とのことで、要するに民間からの手上げ方式で官民連携を進めているんです。
協議が整った後には随意契約でその事業を進めるとのことで、これも画期的です。民間側からしたら、正直なところ入札でとれるかわからないのに毎回提案書作らなければならないというのが、ものすごいコストですよね。随意契約であればやりやすいという企業も多いと思います。公平性が何らかの形で担保できるのであれば、契約や応募というのは、もっと色々なやり方が模索されていいし、柔軟にやっていけるのではないかといったことも考えているんです。

市長ピッチ当日は、3市の市長や関係者、ビジネスパーソン、議員など多くの参加があった
地方議員はポテンシャルが高い
小田 市長ピッチはあくまでもイベント仕立てで実施したので、今後はもっと仕組みとして構築していきたいと思っています。そこには地方議員に是非関わってほしいと希望しています。地方議員のポテンシャルって実はものすごく高いんですよ。
編集部 地方議員のポテンシャル、具体的にどう高いのでしょうか?
小田 地方議員にこの場(QWS)に来て頂き、あなたのまちの課題は何ですかと尋ねると、議員は1時間でも2時間でも話してくれるんですよ。要するに、まちに対する俯瞰力、そして課題発見力は議員さんならではだと。
同じ質問を自治体の職員にしても、人口減少と税収が下がっていることでしょうか…なんて、誰でも知っているようなことが多いのです。そこはとても残念で。
編集部 山梨学院大学の江藤俊昭先生は、地域の課題はすべて議会に集まってくると仰っていいますよね。会議録を見れば、その地域のことが分かる、と。
小田 そうなんです。議員は一つひとつの議案を見ているし、予算や決算の審議を通じて恒常的に数字も見ている。それから職員と違って、毎日まちをぐるぐる歩いて、様々なステークホルダーに会って、直接話を聞いているわけです。だから、まちについて小さな話も大きな話も知っている。そこから培われる俯瞰力と課題発見力なわけです。
編集部 逆に議会の課題は何でしょうか?
小田 今の地方議会の課題は、議論をしないこと、ではないでしょうか。そして、現状の地方議会の構成に多様性がないことも挙げられます。議会の構成は、市民の構成と同じ構成にならないといけないと思います。年齢比や男女比もできればその市の構成に近いほうがいいと私は思っています。
構成が多様になったうえで、お互いの違いを認め合い、「私はこう思うけれど、あなたはどう思う?」という対話を重ねて、議論ができるといいと思います。残念ながら今は、「私は違うと思う」と言うと、「おれのことを馬鹿にするのか」という話になってしまって議論をするのが難しい状況です。これは個々の議員というより議会全体としての課題ですね。
編集部 最近は議員間討議の重要性も指摘されてきていますが、なかなか地方議会に自由に議論する風土が根付いたとは言えない状況でしょうか。
小田 それから、議員の価値・ポテンシャルは、課題発見力、俯瞰力に加えて「調整力」です。議員はステークホルダー間の調整がものすごく上手な方が多いんですよ。
官民連携事業において、このスキルはとっても重要で。地域に対する想いがあって、自分の手柄を殊更に主張しない議員を調整役に入ってもらうとすごくうまくいく。実は既存の官民連携事業でも、議員が入っているということもあるようです。
自分のまちで調整ということになると利益相反ということになってくるので、私たちの会社で議員さんにプロジェクトに参画していただく場合には、自分の自治体以外の場所でお願いしています。
編集部 起業時のメンバーだけで連携事業を行っているわけではなくて、現職の議員さんにも活動してもらっているんですね。
小田 そうです。官民連携事業のリサーチや調整、ファシリテーションなどもやってもらっています。当社では議員を応援するWEBメディア(https://publab.jp/)と議員向けオンラインサロン(https://publab.jp/lp/salon/)を運営しているのですが、そこでつながった方に直接お声かけしたりということで進めています。現在オンラインサロンはFacebook上でやっており、これが約300名、Facebook以外で繋がっている議員さんも含めると約500名の方に参加頂いています。
編集部 自治体議員であればだれでもメンバーになれるのでしょうか。
小田 そうです。沢山の方に入って頂きたいと思っています。地方議員は次の選挙で落ちてしまったらどうしようと思い悩む方も実は多いんです。それは実際に議員を経験してみて実感しています。次のキャリアについて描こうとしても、残念ながら民間企業側には議員というと駅頭で演説をしているイメージくらいしかなくて。
そんな中で、実は官民連携事業プロジェクトでは、こういう役割を担っていましたというところまで可視化できるようになれば、企業側もこういう人材であれば欲しいということになる。そうなると。変な意味で議席にしがみつく必要がなくなる。
だから当社でプロジェクトにご協力頂いた方は、次のステップとして議員でない世界に入りたいというときにもすっと行けるのではないかと思っています。なりたい自分になるということのお手伝いをしているとも思っています。

地方議員のポテンシャルは課題発見力、俯瞰力、調整力と話す小田さん