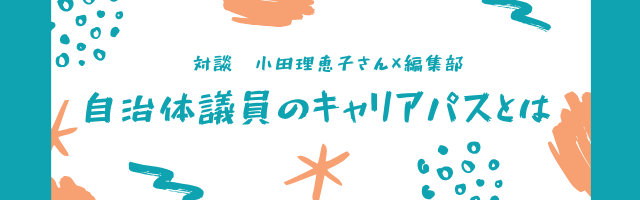8年間で思考のスタイルが変わった
編集部 議員として活動した8年間で、議員になる前と後とで何か変わったことはありましたか。
小田 地方自治に関する理解が劇的に変わりました。そして自分の内面もとても変わったと思っているんですよ。
議員になる前は、合理主義的・新自由主義的な「強い者が勝って、能力のある者が上にあがっていけばいいじゃないか」という考え方でした。でも行政の中に入ると、そういった合理性や効率性ということだけで語れないものや切り捨てられないものがあるということが実感を持って分かってしまって。「ああ、こんな理不尽な環境に期せずしてして置かれる人がいるんだ、自分にはままならない状況で辛い想いをする人がいるんだ」ということに、議員として日々住民や行政に接するようになって気づかされました。
編集部 議員として活動するようになって、実感として社会のひずみが見えてきたと。
小田 今にして思うと、社会には分かち合い、そして支え合いが必要だということを、議員活動を通して徐々に感じるようになったんだと思います。結果として、議員として活動していた8年間で、自分の内面、特に社会に対する考え方がものすごく変わりました。これを、“パブリックマインドが身に着いた”という風に最近表現しているんです。
編集部 パブリックマインドというのは、自分の利己心を満たすだけでなく社会全体のためにコミットしようという意思、ということでしょうか。他方、選挙で恒常的に勝ち抜いていくために、まずは後援会など日常的に応援してくれる方の声が重要という方もいらっしゃると思います。今お話をお伺いして感じたのは、「この人は私を応援してくれるから」という論理でなく、議員活動を非常にフラットに、様々な立場の住民の声を小田さんが聞いてきたからこそではと思いました。
小田 そうでしょうか。困っている人の話を聞いて寄り添うということは、議員であればほぼ皆がやっていることだと思いますよ。それが支援者中心かもしれないし、そうでないかもしれないけれど、「困っている人」という意味では同じことでしょう。
だから、何か困っていることがある、何か障壁になっている社会の何かがある、そんな困っている住民に親身になって、一緒に乗り越えていく、社会の障壁を取り除いていくということは多くの議員がやっていることだと思います。私もその一人になったんだという言い方が正しいかもしれません。
官民連携事業を軌道にのせたい
編集部 小田さんは2019年5月に仲間と(株)Public dots & Companyを起業されて、日々お忙しく活動されていますね。会社のHPには「公共を再定義します」、「官民連携のデジタルプラットフォーム」ですと掲げられていますが、具体的にどういったことを手掛けている会社なんでしょうか。
小田 これまでになかった新しい試みなので、一言で説明するのが難しいのが最近の悩みです(笑)。
まず、“官民連携事業”と呼ばれるものが近年とても増えています。その背景には自治体はこれまで自前で行ってきたサービスをやりきれなくなってきている現状があります。少子高齢化は否応なく進み、行政サービスに対する社会的需要が増えている。需要は増える一方なのに、自治体に入ってくるお金は減って、人もいなくなってきているのです。私は地方議員として行政の中に入って、これはしんどいな、政令市レベルですら維持していくだけでも辛いなというのがわかってきた。全国の自治体でそういった状況です。
だから今、民間企業が担える部分は民間でという方向にシフトし始めている。そうして民間に委ねる部分を軌道にのせ、最終的には自治体は本当の意味で公共としてやるべきことに集中しましょう、これが官民連携事業の基本的な思想です。
私たちが会社を興す前から、国も自治体もこの方向に進んでいて、自治体が持っている資産を民間が活用して地域に還元しましょうという動きが出てきていました。ただ、うまくいかないケースが結構あって。
うまくいかない原因の一つは、自治体の論理と民間の論理が全然違うことだと私たちは考えています。それぞれの立ち位置も言語も違うので、それぞれの論理をそのままくっつけてもうまくいかない。私たちのHPには、「地方議員、公務員を『公共戦略コミュニケーション』の専門家として民間企業とのプロジェクトにマッチングする会社です」とも書いていますが、民間・自治体双方を経験している人が仲立ちをして、もっと実のある、社会にとって価値のある官民連携事業をやりましょうというというのが私たちの提案したいことです。
だから、社会全体にとって価値があるものでなければ手掛けませんし、民間企業だけが一人儲けするようなことも受けません。

自治体の論理と民間の論理は全然違うと言い切る
民間企業にも、事業領域を広げたいというニーズがある
編集部 先ほど仰っていた、利益追求だけでは切り捨てられてしまうような部分を切り捨てずにやっていける、第三の道を模索しよう、社会全体で幸せになっていこうといったパブリックマインドを体感・共有しているメンバーだからこそ立ち上げた会社なのですね。
もう少し具体的にお聞きしたいのですが、例えばある自治体が新庁舎建設を計画しているとして、その際に設計をしたい企業がいる。そんな企業の入札なりプロポーザルの手伝いをするということでしょうか。
小田 それだと口利きに近いですよね(苦笑)。むしろ、対民間企業では「こういう形で自治体に対して一緒に提案しましょう」というスタンスです。ときには提案内容が新しすぎて自治体側からそんなのは飲めないって言ってくることもあるかもしれません。だから、単に入札を手伝うということではないんですよ。
社会が良くなっていくための新しい価値や手法を提案したり、模索したりというのを、自治体や民間企業と一緒にやっていきたいと思っています。
編集部 そうすると、小田さん達の側から提案していくという形の方が多いのでしょうか。
小田 民間企業には新しい事業領域を広げたい、オープンイノベーションをしたいというニーズが特に最近はあります。企業は行政と組んで何かやりたいと思っているんです。けれど、自分達ではどうやったらいいのかわからないことが多いのです。
だから、現在のところ私たちの会社では、民間企業向けに、どうやったらイノベーションができるのかとか、自治体は今こんなところで困っているといった入口の部分のワークショップや研修を多く行っています。
編集部 一自治体の議員という立場からの提案は、企業も自治体も受け入れにくいということってあるのでしょうか。今は市議という立場でなく、比較的自由な立場でいらして。提案の方向性としては市議時代からぶれていなくても、民間企業という立場からの提案だと自治体側は受け入れやすいということはあるのでしょうか。
小田 そういった傾向はあると思いますよ。私が議員時代に辛かったのは、行政に「あれをやれこれをやれ」と言わなければならないときでした。行政にはお金がないと知っているからこそ、それが辛かった。だから、議員として新規事業の提案をするのであれば既存事業の廃止提案とセットでなければと言い聞かせていました。「補助金増やしました」、「新しい事業やらせました」というのは議員個人のPRとしてはすごく良いかもしれませんが、それを続けていては自治体が持続できません。
議員をやればやるほど構造的な課題が見えてくる中で、議員という立場でやれることだけがすべてじゃないな、そして課題解決に先立つものが必要だなと感じました。だから、民間の経済活動を活かして社会的課題を解決できる道を探りたいと思ったのです。