2019.07.25 視察
【取材レポート】地方議会と弁護士の連携の可能性
2019年5月27日(月)、日本弁護士連合会主催の研修会が東京で開催されました。テーマは「法化社会における弁護士の地方議会とのかかわり」。日弁連がこれまで「法化社会における条例づくり」と題して行ってきたセミナーの第5回目にあたります。議員条例提案が少しずつ増えてきているなか、議事機関・議決機関であると同時に条例制定機関である地方議会が直面する法的諸問題を整理し、これらに対する弁護士のかかわり方を検討することを目的として開かれました。
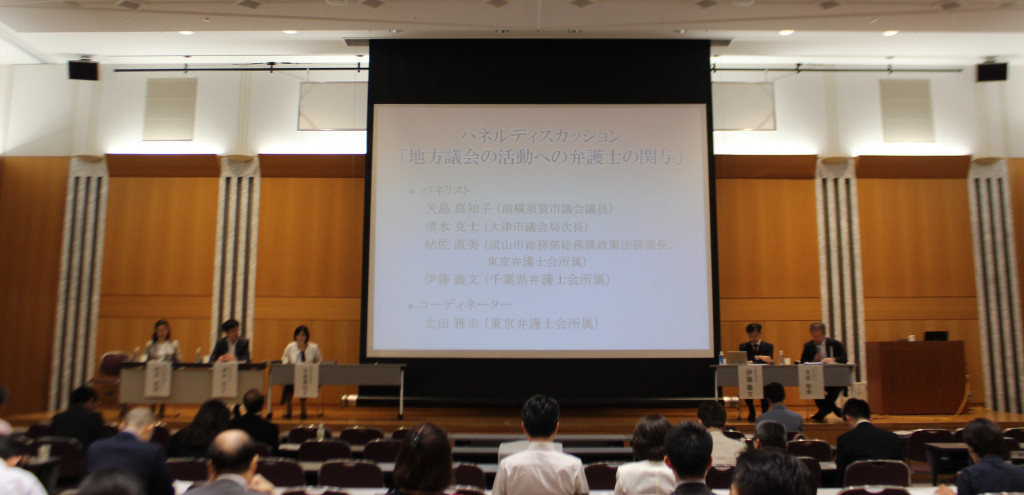
議会の政策法務
第1部冒頭の江藤俊昭氏(山梨学院大学法学部・大学院社会科学研究科教授)の講演では、議会基本条例制定にはじまる議会改革の一連の動きを振り返ったうえで、従来の議会改革は「運営」的要素にとどまっていたのに対し、改革の第二ステージでは「議会からの政策サイクルの作動」が求められると指摘しました。すなわち、政策提案に連続性を持たせること、質問や決議、条例提案など議会の権能をつかいこなすことなどです。

さらに「議会の政策法務」として、議会内のルール策定における「議会への政策法務」と政策立案過程における「議会からの政策法務」の2つがあるのではないかとし、機関としてその法務能力を果たすための条件整備として、議会事務局の強化、議会図書室の充実、専門的知見の活用、議会アドバイザーの導入、大学・研究機関との連携、そして法律家との関係の強化を挙げました。
議会と法律家がかかわる際の留意点としては、地域の課題に関する土地勘があること、任用にあたって議会単独か執行機関との併任かによってかなり勝手が違うことに注意すること、また、議会の特性をよく理解した議会ならではの政策法務を実践できる人材であることが望ましい、などと指摘しました。
所掌事務で縦割りになりがちな執行機関に比べ、総合的に行政をみることができるのが地方議会の良さでありつつも、現状制度では執行機関に比して人的にも財政的にも資源が乏しく、議会が全てをみることが難しいのも現実です。そのあたりの特性を踏まえたチェック機能の発揮が求められます。
専門的知見活用の可能性
続いて、矢島真知子氏(横須賀市議会議員)による「地方議会の政策形成能力強化のための補佐体制」と題した講演があり、同市のこれまでの議会改革の取組みに関して紹介がありました。議会改革の第1ステージとしては、議会活性化推進委員会を設置し、議員の審議会等への参画の見直しや議員研修の定例化、事務局の調査機能強化など取り組んできたほか、議会内のLAN構築や全議員へのノートパソコン・メールアドレスの配布、本会議・委員会のインターネット中継や議員のITスキル向上のための研修やIT化倫理指針の策定など、議会のIT化を着実に進めてきた実績を振り返りました。

また議会改革の第2ステージに入った横須賀市議会では、議員提案条例に非常に活発に取り組み、中小企業振興基本条例や空き家等の適正管理に関する条例、観光立市推進条例、給食条例、不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例などを策定してきました。
さらなる議会改革のステップアップに必要なこととして、議員一人ひとりで動くのでなく事務局も含め「チーム議会」としてまとまること、井の中の蛙にならぬよう他議会との交流をすること、専門的知見を活用し常識をアップデートすることなどを挙げました。専門的知見活用の方法としては、議会の政策立案強化及び立法補佐体制として弁護士や学者等有識者の活用がますます必要であるなか、常勤ではなくアドバイザー契約又は顧問契約という形で、必要に応じて法的アドバイスを頂く形が望ましいのではないかといった指摘がありました。
第一部最後の講演では、「地方議会における政策条例の立案の実情~「未来を語る議会」であるために~」と題して、大津市議会のこれまでの取組みについて解説が清水克士氏(大津市議会局次長)によりありました。大津市議会では、議会の政策立案のためのスキームとして、全会派が参加する「政策検討会議」を設けています。そこでは政策の提案会派が座長をつとめ、各種政策テーマについて議論しているとのことです。これまでの実績としては、議員政治倫理条例、いじめ防止条例、議会BCP、議会基本条例、災害等対策基本条例、いじめ防止条例の改正案、議会ミッションロードマップ、がん対策推進条例など多くの成果を出しています。このほか、大津市議会では、大学とのパートナーシップ協定の締結や、議会例規体系の見直し、議会意思決定条例の制定など、従前の慣習にとらわれない改革を進めています。

講演の最後に、清水氏は、今後の議会と弁護士との連携可能性については、①政策条例案の法規適合性に関する助言、②政務活動費使途の適正性評価、③100条調査業務委託、④執行部提案条例の法規適合性審査、⑤議員資格等に関する助言などを挙げました。
議会活動への弁護士の関与
第2部のパネルディスカッションは、テーマを「地方議会の活動への弁護士の関与」として、コーディネーターを太田雅幸氏(法律サービス展開本部自治体等連携センター委員、弁護士(東京弁護士会))が務め、パネリスト4名(矢島真知子氏、清水克士氏、帖佐直美氏(千葉県流山市総務部総務課政策法務室長、弁護士(東京弁護士会))、伊藤義文氏(法律サービス展開本部自治体等連携センター委員、弁護士(千葉県弁護士会)))の議論が繰り広げられました
議論のなかでは、議員による政策検討の際の議会事務局のサポートの状況、事務局が出すぎると議員が頼り切りになってしまうというバランスのとり方の難しさ、議会を支えるマンパワーとしての議会事務局の更なる強化についてなど様々な観点から議会の政策提案能力の向上のための検討がなされました。
そのうえで、執行機関との併任で議会事務局書記として議会からの法律相談にも対応している帖佐氏からは、併任ならではの悩みとして、執行部提案の議案の課題について率直に問われたときに、どのように回答すべきなのかは難しいとしました。これに対して、矢島氏は弁護士を執行機関と議会で併任するケースの限界を感じるとコメントしました。
議会事務局職員の充実については、横須賀市議会ではかつて25名だったところ、現在は非正規含め20名体制であり、人員が減っていることもあり、雑務は極力減らし、出来るだけ政策的な事案の補助のほうに力を入れられるようにしてあげたいと思っていると矢島氏は語りました。
また、清水氏からは、大津市議会で議会BCPを策定した際には新川達郎氏(同志社大学教授)に専門的知見としてサポートに入って頂き、知見を頂くだけでなくファシリテーター的な役割も担っていただいたとのコメントがありました。
議会の100条委員会のサポートをした経験のある伊藤氏からは、100条調査では事件について何が起こって何が違法とされるのかを整理するが、これは裁判における事実認定と似ており、弁護士にはうってつけであること、ただし時間の制約もあり、弁護士1名で100条調査にすべて対応するのは証拠や資料あつめ、報告書の作成など多岐にわたることもあり、マンパワー的になかなか難しいとの意見もありました。
続いてコーディネーターの太田氏から、「弁護士に何を期待するのか、求めるものは何か」という問いかけがなされ、これに対して矢島氏は、議会が作った条例が体を成しているのかという確認程度であれば、併任の弁護士で構わないと思うが、そうではなく、政策条例策定の協議会などに検討当初からかかわってもらい、ビジョンから共有しながら一緒に作れるという体制が望ましいと思う。しかし政策条例を恒常的に作っているわけではないため、常勤ではなく単発のアドバイザー的なものが良いのではないかといった意見が出されました。また、これまで専門的知見の活用というと、大学の先生に依頼するということばかりであったが、テーマによっては弁護士のほうが適しているということもあると気づいた、といったコメントもありました。
最後に、江藤氏は、今回のセミナーが新たに議会と弁護士との連携を模索する第一歩として、非常に良かったと総括しました。そもそも議会が条例づくりを熱心にやる必要があるのかという議論は別にあるものの、まずは首長提案の議案をしっかりとチェックすることや既に制定されている条例をチェックすることなどが必要であり、そのために議会局の充実、並行して、機能の外部化の議論も必要であり、その際に弁護士と議会がどのように連携できるかということが、今後具体的に議会改革の検討の遡上に載ってくるとし、このような連携の可能性を探る機会はこれまでにないものであり意義深いと高く評価しました。








