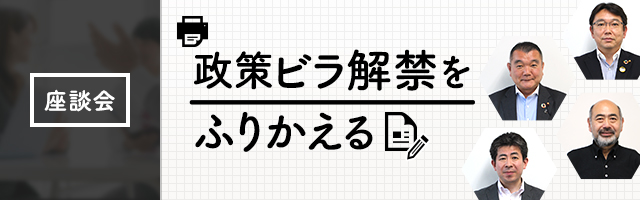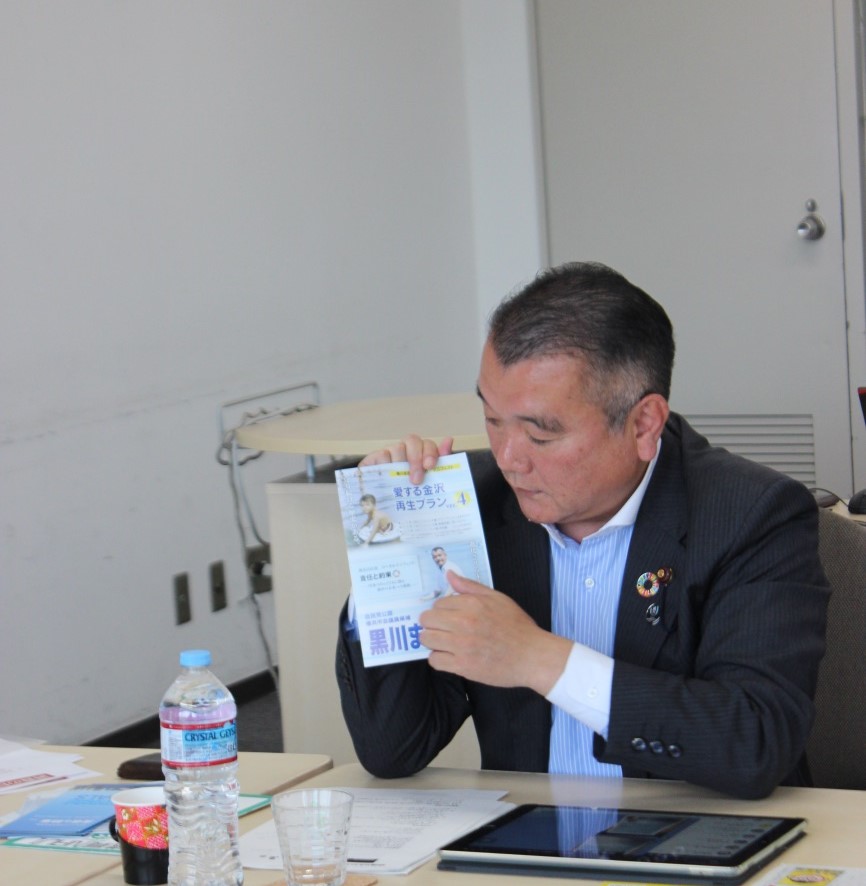政策ビラへの住民の反応はどうだったか
青木 ビラをもらった住民の反応はよかったですか。
黒川 有権者の反応としては、選挙前よりも選挙期間中の方が、格段によかった感じがしました。普段の2~3割増しくらいの数を受け取ってもらえました。
佐藤 住民の反応はとても良かったですよ。(イラストの紙面を提示して)4年前にはこのイラストで選挙ポスターを作成したので、有権者の印象に残っているだろうと考えて、今回の政策ビラでも活用することにしたんです。前の座談会の時に、政策ビラは、受け取った後に「捨てられないものを」というアイデアが出ました。この「捨てられない」という切り口で考えて作成した政策ビラは、実は「お面」風です。
住民が覚えてくれていると考え使った、イラスト
佐藤 この政策ビラを持っていると「何ですかこれ?」って有権者に結構反応してもらえます。そこで、「これはね」って説明する。「法律が改正されて、今回からこういうものが正式に渡せるようになったんですよ」「ぜひ読んで下さい」って、今回政策ビラが解禁されたことなどを説明しながら渡すようにすると、大体快く受け取ってもらえました。「数に限りがあります」なんて言うと、ありがたがってくれたりもして。ただ無言で配るのはだめです、街頭演説をしながら配ります。
青木 世代ごとに反応の違いなどはありましたか?
佐藤 世代でいうと、特に若い人たちや子どもたちに評判がよかったように思います。子どもたちが寄ってくると、まわりの親御さんたちも興味を持って来てくださる。そして、「私の政策は詳しくはここに書いてあります」って渡すと、結構真面目に読んで下さった。だから、手渡しの作戦は効果があったと自分では思っています。
政策ビラが禁止されていたこれまでの選挙では、街頭演説をしているときに「あなたはどういう人なの?」って聞かれても、名前だけ、そしてタスキとポスターを示すことくらいしかできませんでした。でも、これからは、有権者に対して形のあるものを渡すことができる、そのことが画期的だと思いました。
青木 前は顔しか売れなかったのが、今回からは有権者に政策を手渡せるようになった、ということですね。
政策ビラの中身の工夫
青木 政策ビラの中身についてはどんな工夫をされましたか。
佐藤 ちょっとした工夫ですが、実は政策ビラの裏表で、眼鏡のイラストと、円グラフの部分の位置を合わせる工夫をしています。そんな工夫が、街頭で話していると結構受けるんですね。「あ、ピッタリ合ってる!」って。コミュニケーションのためのツールとしても、このビラは本当にありがたかったです。
青木 そういう切り口、とても良いですね。
黒川 私の政策ビラは、表紙には、子供時代の自分と今の自分を同じ場所で撮った写真を使いました。撮った場所は私の家の近所の海岸なんです。横浜市内で唯一埋め立てられていない自然の海岸です。これまでの選挙ポスターや名刺に長く使ってきたもので、大勢の方が覚えて下さっている写真と考え、政策ビラでも使いました。
中身としては、任期中にやったこと、現在やっていること、これからやることを中心に政策ビラをまとめました。
有権者から好評だった写真を主軸に政策ビラの表紙を組み立てたと説明する黒川氏
黒川 ところで私は横浜自民党の中で広報委員長という職を務めていまして、今回の選挙では党内34人の候補者のビラをすべてチェックする役割を担いました。党としての制約はそれほどないのですけれど、議会の中で争点になるIRや中学校の給食などの部分については、党として考え方に沿ってチェックしました。
青木 各候補者の政策ビラをチェックされてどんな印象を受けましたか?
黒川 表面は選挙ポスター、裏面は選挙公報に準じて作る、というものが多かったように思います。それから横浜自民党の政策としてSDGsを打ち出していますが、それに準拠してビラを作るタイプ、推薦人を多く掲載するタイプなど、さまざまなタイプの政策ビラを見ることができ、非常に興味深かったですよ。ちなみにビラを2種類作ったのは、私のほかもう一人、2名だけでした。
青木 皆さん、QRコードは選挙ビラに入れましたか?
川名 入れましたよ。期間中はブログの閲覧数が伸びました。それがQRコードからのアクセスが増えたおかげかどうかはわからないけれど。いちばん伸びたのが月曜、次点が日曜。有権者は投票前にチェックしていたんじゃないかなとも思います。
黒川 私はポスターにもQRコードを入れました。YouTubeにも動画を載せていて、そこにリンクするように仕掛けているのですが、動画自体は7千回程再生されましたが、QRコード経由のアクセスは20数件にとどまりました。どこまで効果があったか…。
田中 カメラで掲示板のQRコードを撮るより、候補者の名前で検索した方が早いですもんね…。
QRコードの是非について語る田中氏
青木 皆さんのQRコードからはどこに飛ぶように工夫されているんですか?
黒川 いろいろですよ。動画やHP、個別の政策と、3つのQRコードでそれぞれ見えるようにしました。
佐藤 私はHPのトップに飛ぶようにしています。選挙期間中は、HPに普段の4倍のアクセスがあります。もともとが、最近少ないからというのもありますが。昔ほどブログが見られなくなっているように思います。
川名 私はブログのトップです。ブログは毎日更新しているので読んでほしいと思っています。
田中 研究データでも、インターネット選挙を解禁したからっていって期間中に選挙情報をネットで接するようになった候補者の割合は高くなってないんですよね。
佐藤 でも、動きがあることを発信し続けていると、反応や手ごたえがあるなと思います、駅とかで「見てますよ」って言ってもらえる。政策ビラは今回から解禁されましたが、有権者に政策を伝えるチャンネルが幾つもあるって大事です。
青木 以前実施した選挙に関する調査では、有権者は、候補者のHPはより見るようになって、より役に立っていると結果が出ています。ですから、情報の集積地としての価値はあると。若者しか利用していなかった5年前に比べると、最近はようやく50代も参考にし始めたので。もうちょっと時間はかかると思いますが、ネットを活用した選挙の可能性はまだまだ広がっていくと思います。
「ネット選挙の可能性はまだまだ広がっていく」とする青木氏
田中 2018年のLM調査を見ても、有権者が自発的に取得する情報は参考にする割合が多く、ポスターや街宣車のように自然に入ってくる情報は印象があまりよくないんでしょうね。
青木 最近は名前の連呼も印象よくないですものね。