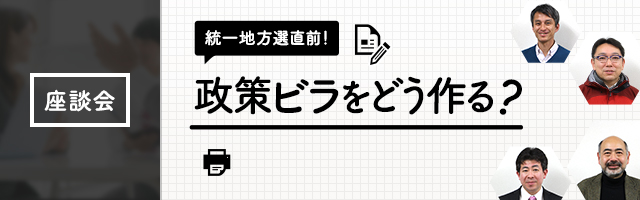いよいよ4月に迫る統一地方選挙。今回の選挙から解禁される、選挙期間中の政策ビラについてLM推進連盟の地方議員メンバーに、徹底的に議論をして頂きました。良い政策ビラとは何か?政策ビラの作成に悩む皆さま必見です。ぜひご覧ください!今回は中編をお届けします。
目次
(上編 2019/2/18公開)
1 政策ビラ解禁、各議会の反応は?
2 選ぶ・選ばれるチャネルが増える
3 公費負担条例の制定状況は?
4 「届け方」にもテクニックがある!?
(中編 2019/2/25公開)
5 政策ビラ、どう作る?
6 ここでおさらい、政策ビラ解禁の意義とは
7 政策(マニフェスト)の評価・検証という難題
8 議員にとっての政策(マニフェスト)の達成とは何か
(下編 2019/3/4公開)
9 政策ビラに必要な要素は?
10 新人議員と現職議員で政策ビラに盛り込む内容は変えるべき?
11 政策ビラと他のツールの連動も考えよう
12 選挙が変わる、政治が変わる、そのターニングポイントにしよう!
番外編 インフラとしての政策ビラ。その保存を考える。
5 政策ビラ、どう作る?
青木 前向きな話になってきたところで……ここまでのお話では事前に配るチラシとさほど内容を変えないかもしれないという意見もありました。とはいえ、こんな内容を盛り込みたいとか、デザインとか表現とか考えてらっしゃることはありますか。
佐藤 今までは、例えば選挙公報について言えば、掲載する内容を一生懸命考えに考えて、他の候補者と差別化をしたつもりで作っても、結局刷られたのを見ると埋没しているということが多かったです。とはいえ、今回の政策ビラだって考えて考えて、自分の伝えたい内容を詰めると思います。有権者が読んでくれることを信じて。
白井 サイズはA4以内ということですから、A4より小さくてもいいんですよね。実は小金井市の選挙公報はB5サイズだから、選挙公報と政策ビラが同じでもいいということになります。
田中 ちなみにA4サイズ内であれば、形を丸く、厚紙に印刷をして穴を開けるということも良いようですよ。豊島区のHPで公開されている「選挙運動用ビラに関するQ&A」が非常によくできていまして、そこに詳しい説明があります。
穴が開いている分には良いそうです。でも、柄が付いているのはうちわとみなされて、利益供与になるそうです。形状及び紙の厚みに決まりはないのですね。ただ、紙の厚さは均等でなければだめだそうです。折り紙のような立体はNGです。
白井 紙ツールはやりようによっては非常に工夫ができますね。「超厚紙で作ったチラシは捨てられない」という分析もあります。
あと、候補者がみんな揃って普通のA4サイズのチラシしか配らなかったら、いくら中身のデザインに凝ったとしても、有権者側としては「あまり面白くないよね」って受け取った段階ではじかれちゃう可能性があります。そこで、他の候補者のビラよりも紙を厚くするなど工夫して、まず印象には残って捨てられないようにするとかどうでしょうか。
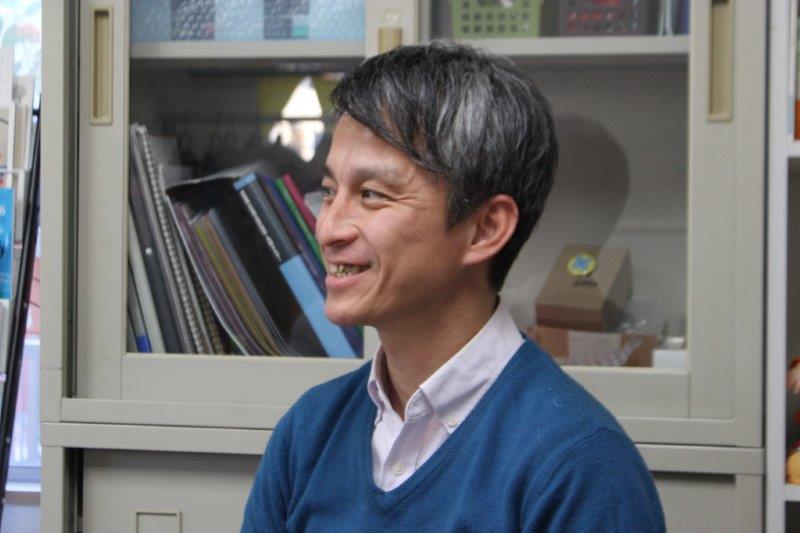
(写真)紙ツールはやりようによっては非常に工夫ができると語る白井議員
佐藤 読んでもらう以前に、まず入り口としてもらってもらわないと、ということですね。
青木 どんな人にどう届けてどう読んでほしいかまで考えると、工夫ができるということですね。
白井 最近増えてきた手法ですが、政策をマンガにすると、読んでもらえる率は高くなりますよね。
しっかり伝えなきゃいけないことは何か、受け取ってもらうためにどうするか、読んでもらえるためにどうするか。そこはしっかり考えればやり方がある。
でも、例えば候補者が30人いたとして30人がビラを作って一斉にビラを配るとなると、有権者としては途端にめんどうくさくなっちゃうんですよね。「情報はいくつかあると選択できるけど、ありすぎると選択できなくなっちゃう」というのが行動経済学でいうところの分析なので、そういったときに一風違うものを用意するというのが大事。
佐藤 そういうビラだったらもらおうか、みたいなものですよね。
青木 有権者目線ですね。
佐藤 あと工夫で言えば、折り方をどうするかという観点もあります。2つ折りがいいのか、4つ折りがいいのか、観音開きや冊子になる折り方もある。
白井 受け取りやすいのか、そもそも見やすいのか、それが重要ではないでしょうか。
佐藤 A4サイズ2つ折りは配りやすいし、受け取りやすいと思いますよ。
田中 私はA4サイズ3つ折りです。これだと封筒に入れやすいという利点があります。
青木 沢山アイデアを頂きました。テクニック面でも工夫できることが沢山ありますね。