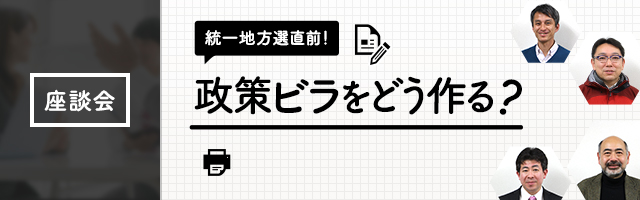2 選ぶ・選ばれるチャネルが増える
青木 ここまで色々と皆さんのお話聞いてきましたが、予想以上に、盛り上がってないのではと不安になっています…。
川名 私は政策ビラの解禁を積極的に評価していますよ。これまでの選挙運動では、「街頭演説はうるさいからやらない」というポリシーでした。でもそうなると、立っているしか出来ずやることがあまりないんです。あまり意味がないのではという想いもあったので、今回は政策ビラを配れるようになりありがたいです。
白井 それに、新人として選挙に出る人の視点から見てもありがたい機会だと思います。現職議員はそれまで議員として活動しているわけで、仕事をしっかりしてれば、名前もある程度知られています。
でも新人は名前が知られていないケースがほとんどです。この新人は何を考えているんだろうという有権者の疑問に対して、選挙期間中に政策ビラをまけるようになったというのは、新人議員が選挙で不利な状況に陥りがちな現状を覆すチャンスでもあるんだろうなと思います。
自分自身、新人として出馬した際に、「何故選挙期間中に政策を示したビラをまけないんだ、どう考えても現職有利じゃないか」と思っていました。
川名 有権者にとっても、政策ビラの解禁はすごくいいことだと思いますよ。有権者から見たら「候補者が多くて何が何だか分からないし、朝は時間ないから演説を聞く時間もないし」というのがこれまでの地方選でした。候補者ごとに政策がまとまっているビラを貰えた方が分かりやすく有り難いと思います。
佐藤 こちらが街頭演説しているときに「政策ビラをください」っていってくる有権者、これまでもいましたよね。
川名 いましたね。
佐藤 これまでだったら、「選挙期間内は配れないんです、申し訳ありません」って説明するしかなかったですもんね。
青木 従前、選挙期間中には候補者の名前ばかり連呼するしかなく、有権者からは迷惑と批判されるということがありましたけれど、逆に公職選挙法上それしかできないという背景がありました。
佐藤 選挙で投票する先を「候補者の政策を見て真面目に考えて決めたい」と考える有権者にはいいと思うし、立候補者としても真面目に政策を伝えて、そのうえで決めてほしいと思うので、政策ビラは大事なツールです。だからこそ、政策ビラの内容がきちんと作られて、そしてそこに嘘が書いてなければいいと思います。
川名 確かに。ただ、政策ビラの内容の話と、配る/配らないの話は分けて考えないと、分かりづらくなりますね。有権者に伝える内容の正確性の担保は、選挙期間を問わず考えなければならない内容です。
3 公費負担条例の制定状況は?
青木 ところで皆さんの議会では公費負担条例を制定しましたか。
佐藤 12月議会で通しました。
白井 9月議会で対応しました。
田中 私の議会も9月議会での対応です。
青木 全国の議会の制定状況については、全国市議会議長会に確認してみましたが、残念ながら特に調査はしていないようです。ここはマニフェスト研究所としては調査すべきかなと思っています。今後、議会改革度調査の調査項目に盛り込む予定です。
ところで、公職選挙法では政策ビラは解禁されましたけれど、公費負担の条例が制定されてない場合どうなるんでしょう。
白井 その場合は自費で制作することになりますよね。
川名 条例がないけど政策ビラを配布したいという場合でも、公選法違反ということにはならないと思います。制作を公費で負担するかどうかというのは考え方の問題ですから。
青木 そもそも政策ビラを作らないというケースもあるんでしょうか。
田中 作る/作らないという判断について、コストの側面から考えてみたいと思います。
まず政策ビラ一部7.51円というのが公選法上のMAXの額ですが、この価格ですべて賄うというのは中々難しい現実があります。
もうひとつは、実際のところ、政策ビラをどう配るのかという問題があります。そして現状、新聞折込を利用する以外には中々捌けないという現実があると思うんですよ。
このようなことを考えたときに、今までビラの配布を行ったことない人たちが果たしてそこにお金をかけてまでやるかということについて、若干私は疑問があります。特に新聞折り込みにかかる費用には公費を充てることはできませんから、全部自費ということになります。そういったコストと、ビラを配布する効果を考えたときに、それでも政策ビラを作る判断をするのかということには、個々人によって温度差があるかなと思います。

(写真)費用対効果についてよく検討すべきとする田中議員
青木 たしかに、ビラの制作に対しては公費が出ますが、届けるための費用は別ですね。
川名 コストがかけられないというのであれば、期間前のものと極力同じデザインで政策ビラを作るということもあり得るのでは?