2017.06.26 選挙
【選挙プランナーのサクセス情報】今どきコンプライアンス最新事情[PR]
いよいよ都議選が告示され、選挙戦がスタートしました。毎年のように改正のある公選法。18歳選挙権解禁を受け、2017年2月に改訂された『地方選挙実践マニュアル-改訂版-』から選挙のコンプライアンスをテーマにした部分を抜粋して紹介します。(編集部)
選挙プランナー/アスク株式会社代表取締役社長 三浦博史
今どきコンプライアンス最新事情
選挙に関わるコンプライアンス事情はここ一〇年ほどで大きく様変わりしました。
一昔前までは、「(選挙プロは)選挙違反を怖がっていたら選挙には勝てない」などとよく言われたものでしたが、私は当初から「選挙プロが入ったら選挙違反は絶対に出さない」をモットーに活動してきました。今ではそれが当たり前の時代となったのです。
そもそも、選挙違反の多くは「無知」からくるものが多いのです。「市民目線の選挙戦」を標ぼうし、できる限り、これまで選挙に携わってきたような人(俗にいう選挙の手あかがついている人)は選挙対策本部に入れず、いわゆる「手づくりの選挙運動」をめざそうとする姿勢はよく理解できます。しかし、そこに“落とし穴”もあるのです。なぜなら、“選挙のルール(公職選挙法・政治資金規正法)”を知っている人が皆無の状態では、選挙違反が生じる可能性が高いからです。
選挙はスポーツと同じで様々な最低限のルールがあります。ルールは事前に学び、守るべきです。そして、そのルールは選挙の種類によっても微妙に異なるのです。したがって、素人集団が見よう見まねで選挙戦を戦うことは危険な面も常につきまとうのです。
たとえば、市議会議員選挙に手慣れた人が市長選挙を仕切る場合や、市議ひとすじに活動してきた人が市長選挙に立候補する場合にも同じことがいえます。同じ公職選挙法といえども、(市議選では)常識だったことが、市長選では全く通用しない(もちろんその逆もあります)、市議選では認められていないことが市長選では認められる、といったこともあるのです。さらに、選挙違反に関するこれまでの常識も大きく様変わりし、「今まで大丈夫だったから」「他陣営もやっているから」などといったことは通用しなくなってきました。
私はこれまで数多くの選挙戦に携ってきましたが、その度ごとに公職選挙法等も逐一チェックしながら、新たな候補者の歴史をつくるという姿勢で臨んでいます。まず最初は慣れている人から簡単なルールの説明とケーススタディ等を聞き、疑問が生じたら専門家からアドバイスをもらったり、わかりやすいマニュアル本を参考にしながら取り組むことが必要です。そして、少しでも疑問や迷いが生じたら当該の選挙管理委員会に相談、確認することです。およそ全国どこの選挙管理委員会も丁寧に教えてくれるはずです。ただし、窓口によって指導の内容に若干の温度差があるのも事実です。
選挙違反について
我が国の公職選挙法は、インターネットはもちろん、屋外のビジョン広告などのなかった時代に制定されたものです。したがって、ウエブサイトやブログ、ツイッター、動画などを「文書図画」というひとつのくくりで規制すること自体、大きな無理があります。
選挙戦の基本は、顔と名前を覚えてもらい、自らの政策(主張)を伝え、一人でも多くの人に投票してもらうことです。そのためには一軒一軒訪ね、自らを売り込む個別訪問は世界のどこでも当たり前の手段なのです。
しかし、我が国では「戸別訪問」は禁止されています。このように、日本の公職選挙法はグローバルスタンダードからすれば、甚だ時代遅れの不合理な点の多い法律といえるのですが、選挙を戦う以上は、法律を遵守しなければならないのは当然のことです。
ただし、制限速度八〇キロの高速道路上で「三キロとか五キロくらいならオーバーしても大丈夫ですか?」と尋ねられたら、皆さんはどう答えますか? 特に他の車がみんな一〇〇キロ出しているのに、自分の車一台だけが八〇キロ以内で走行しているというのもいかがなものかという見方もあるでしょう。
このように、違反文書を作成して大量に頒布したり、買収や供応のような、“うっかり”とはいえない選挙違反は絶対にしてはならない反面、多少のスピードオーバーなどのようなことまで、どこまで遵守すべきかについては机上論では言えないものもあるのです。
「公職選挙法は、一体何ができて、何ができないのか、よくわからない」という話をよく聞きます。少しでも疑問な点があれば、政党の公認候補の場合は所属する政党のコンプライアンス室へ、無所属の場合は当該選挙区の選挙管理委員会、もしくは所轄の警察に問い合わせることをお勧めします。ただし、その場合、“当局”のアドバイスは、「たとえ一キロであろうと、オーバーしてはいけません」が模範回答であるということもお忘れなく。
…続きは下記書籍でどうぞ!
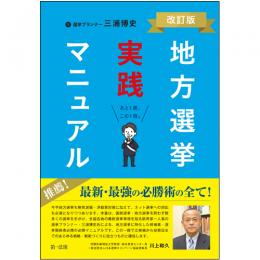
『地方選挙実践マニュアル-改訂版-』
定価2,160円 (本体:2,000円)
著者 三浦博史
2017年2月発行








