2016.10.11 マニフェストスイッチで変わる、政策のあり方・伝え方
マニフェストスイッチで変わる、政策のあり方・伝え方
スマートフォンが政策と有権者を近づける
2016年6月の沖縄県議選では、沖縄タイムスと協力して、全13選挙区 71候補の情報を収集し、公開した。共通フォーマットに加えて、さらに沖縄タイムス独自のテーマとして「基地への考え方」、「経済振興どうする?」、「貧困問題どう解決?」、「子育て支援策は?」、「雇用を増やすには?」も聞いている。
これらを、政策を比較するウェブサイトとして掲載するだけでなく、候補者の事務所で顔写真をピン立てし、地図上で候補者の政策を比べる「沖縄県政策マッピング」を公開している(図2)。「地図で政策を比べる」という新しい政策や選挙の見せ方であり、翁長県政に対する支持・不支持・中立の態度は顔写真の縁取りの色合いを変えて情報提供するなどの目新しさもあり、特に政策マッピングは、TwitterやFacebookで多くのソーシャル・アクションを引き出した。ウェブサイトと政策マッピングは、告示前から投票日後の約2週間で約25万ページビューを記録し、PCとスマートフォンの閲覧比率はほぼ半数だった。また、閲覧者の年代割合も18~34歳で約半数、18~44歳でいえば約8割となった。こうした傾向は、ウェブサイト大手のニュースサイトなどでも見られているという。
 図2 政策や県政への姿勢がビジュアルに一目で確認できる沖縄県政策マッピング
図2 政策や県政への姿勢がビジュアルに一目で確認できる沖縄県政策マッピング
これまで遠かった有権者と選挙や政策情報の距離を、スマートフォンが近づけている。若者たちもこれまでより容易に政治の情報に触れられるようになっている。あと5年、10年もすれば、あっという間に政治や選挙の情報が若者にとって「身近なもの」になる時代が来る。今、マニフェストスイッチにIT技術者の関わりが増えていることや、人工知能「AI」の興隆も考えれば、時代の変わり目に差しかかっているといえる。
地方紙が選挙報道を変える
マニフェストスイッチが約1年間に、いくつかの選挙で一定の有権者の認知を得られたのは、「選挙報道を変えたい」という地方新聞紙の記者たちの思いと行動力が根底にある。ある記者は「これまで、新聞の紙幅の制限や中立・公平性の観点から、新聞紙では有権者に投票に資する十分な情報を提供できていなかった。特に地方紙は、ウェブを活用すればできることはもっとある」とし、特に議会議員選挙における情報提供の不足を悔いていた。彼らの思いと、マニフェストスイッチが目指している「政策型選挙」のベクトルは同じなので、違和感なく手を組むことができた。
これまで実施順で、神奈川新聞社(海老名市長選・市議選、参院選)、熊本日日新聞社(熊本知事選)、沖縄タイムス社(参院選)、北陸中日新聞社(参院選)などの地方紙と連携してプロジェクトを推進してきた。
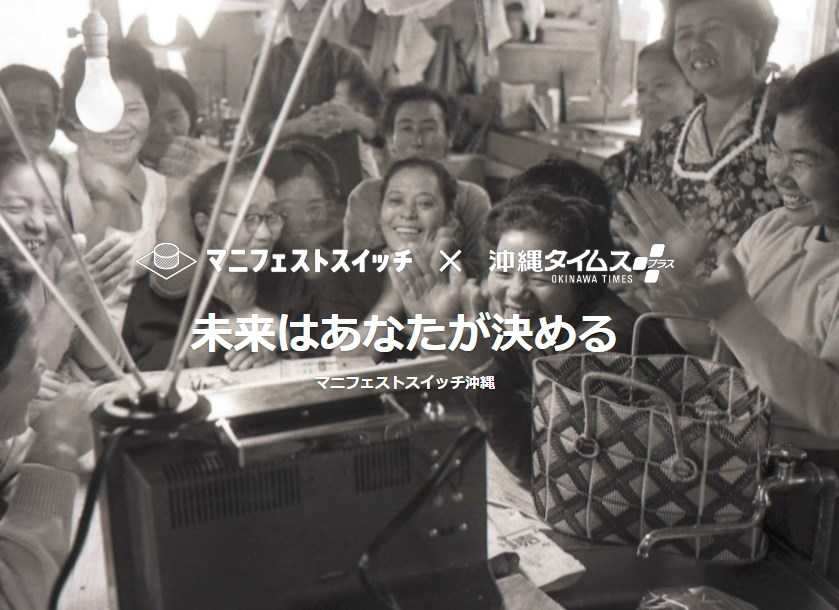 図3 「選挙報道を変えたい」という地方紙の記者たちの思いと行動力がマニフェストスイッチの根底にはある。
図3 「選挙報道を変えたい」という地方紙の記者たちの思いと行動力がマニフェストスイッチの根底にはある。
そもそも「候補者へ共通フォーマットでアンケート」という手法は、選挙のたびに新聞社や青年会議所が実施しているもので、追加的な手間暇をほとんどかけることなく、新聞、テレビ、その他メディアでもできる。もっと多くの地域で選挙を「政策を比べて選ぶ」ものとすべく、共通フォーマット自体の提供は無償で行っている。ぜひ思いを同じくするメディアとは積極的に協力していきたいと思う。








