2021.07.12 住民参加
【第5回】持続可能な議会を目指した住民とのコミュニケーションのあり方~北海道鷹栖町議会の取組み~
早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員 佐藤 淳
|
《今回のキーワード》
|
議員のなり手不足問題はなぜ起きるか
地方議会議員選挙、特に小規模町村議会における無投票当選の増加の傾向が強まっている。総務省の調べによると、2019年の統一地方選挙における、改選定数に占める無投票当選者の割合は、町村議会議員選挙で23.3%となっている。無投票当選のほか、選挙における定数割れが生じる等、議員のなり手不足問題は深刻だ。
なり手不足による無投票当選は、代表者が固定化されることにつながる。町村議会議員の属性は、男性が89.9%(総務省調査、2018年12月31日現在)、年齢は60歳以上が77.1%(全国町村議会議長会調査、2018年7月1日現在)と、ただでさえ著しく偏っている。議会の意思決定には住民の多様な意見を反映させることが必要であり、その前提として議員の多様化は不可欠だ。
今後、人口減少、高齢化の進展は避けられず、全国で議員のなり手不足の問題は確実に深刻さを増す。無投票、定数割れが常態化すると、住民自治の根幹としての議会が、その求められる役割を果たせなくなる。持続可能な町村議会をつくるにはどうすればよいか。
議員のなり手不足の問題には様々な要因が考えられる。議会の活動が不透明・非活発であり、議会、議員の魅力が衰退している。議員報酬が低いといった条件面の問題。地方公共団体との請負を禁止する兼職・兼業禁止等の法制度の拘束等である。
少し古いデータになるが、早稲田大学マニフェスト研究所が2014年7月に実施した、全国の有権者を対象とした地方議会に対する意識調査(有効回答数1,122人)によると、地方議員のイメージの上位は、「何をしているかわからない」(56.1%)、「いてもいなくても同じだ」(34.9%)、「支援団体(地域や団体など)の利益を考えている」(24.7%)と、寂しい結果になっている。議員のなり手不足の解決への第一歩は、議会、議員の活動を住民に知らせ、興味、関心を持ってもらうことである。
今回は、2020年の第15回マニフェスト大賞で、優秀コミュニケーション戦略賞を受賞した北海道鷹栖町議会の取組みを紹介しながら、持続可能な議会を目指した住民とのコミュニケーションのあり方について考えていきたい。
興味を持ってもらう、理解を深めてもらう、参加してもらう議会を目指して
北海道鷹栖町は、北海道中部の上川郡にあり、旭川市に隣接する人口6,700人の町である。議員定数12人の町議会議員の選挙は、2019年4月の選挙で3回連続無投票。町政への関心の薄さに危機感を持った議員が、「できることから、まずやってみよう」というスタンスで、議会広報広聴常任委員会を中心に様々な取組みに挑戦している。
鷹栖町議会では、所管する事務が増えたこともあり、2019年の改選後より、木下忠行議長以外の11人全議員が、議会広報広聴常任委員会のメンバーである。委員会では、片山兵衛委員長を中心に、興味を持ってもらう議会、理解を深めてもらう議会、参加してもらう議会、を活動目標に掲げて以下のことを行っている。定例会に合わせた年4回の議会報の発行。定例会の内容を速やかに紹介するための議会報速報版の発行(おおむね定例会開催1月後、A4判両面1枚)。過去の議会の一般質問のその後を追跡し、質問事項について町として現在どのように取り組んでいるかを伝える「追跡リポート」の発行(年1回)。議員が直接地域に出向いて町民の意見を聴く「地域を語ろう会」の運営とその結果を知らせる報告紙の発行。そして、町民に議会傍聴を呼びかける定例会の傍聴案内チラシの作成等である。
以下、鷹栖町議会の議会広報広聴委員会が担う住民とのコミュニケーションについて、興味を持ってもらう議会、理解を深めてもらう議会、参加してもらう議会に分けて、その具体的な取組みを紹介する。
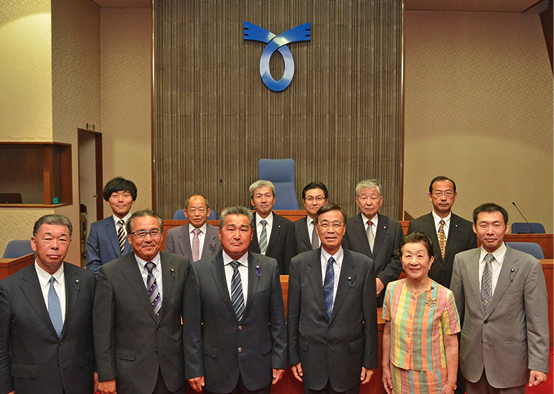
鷹栖町議会議員の皆さん








